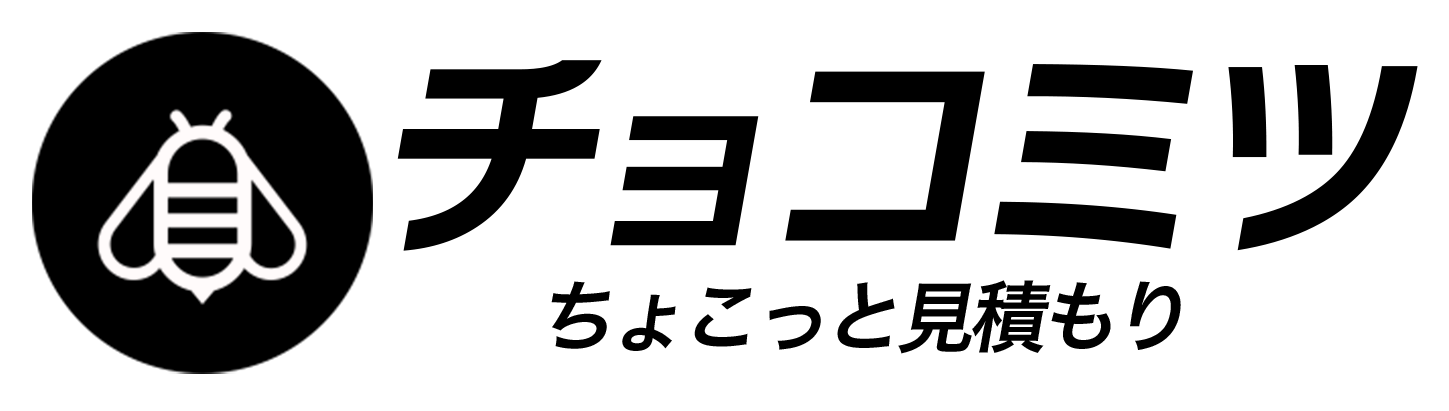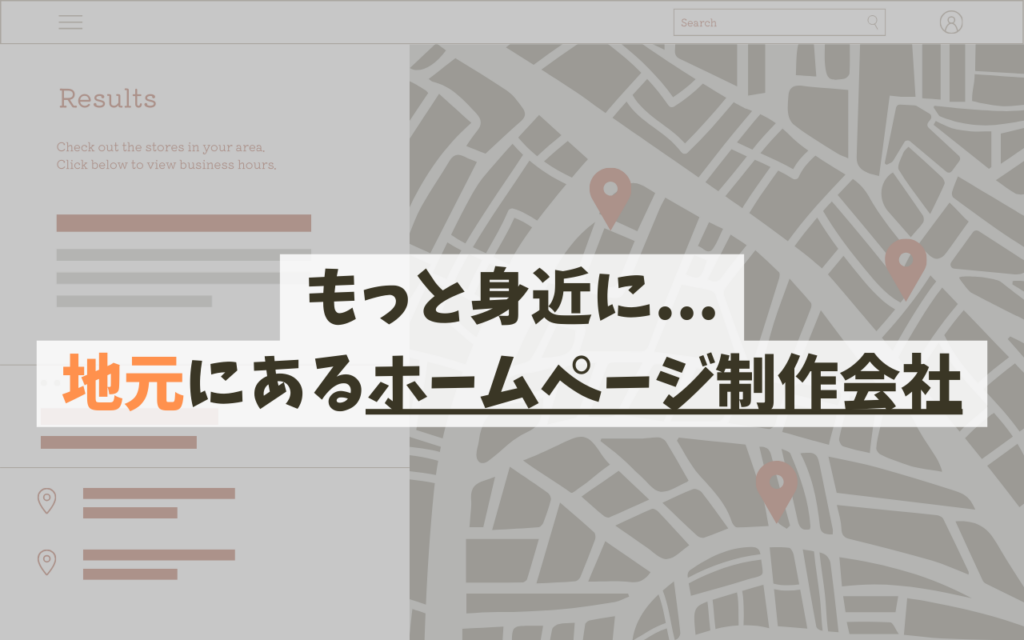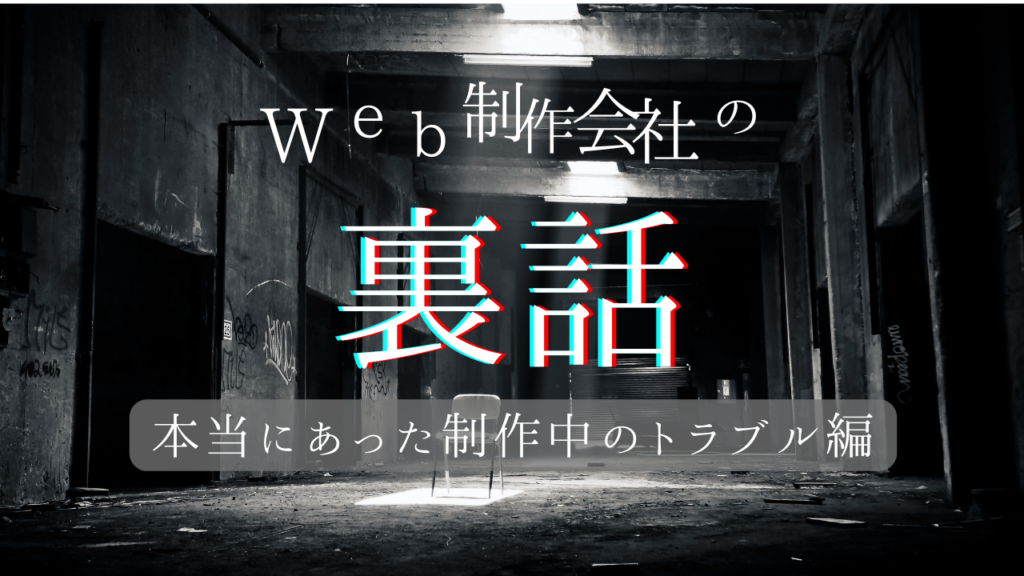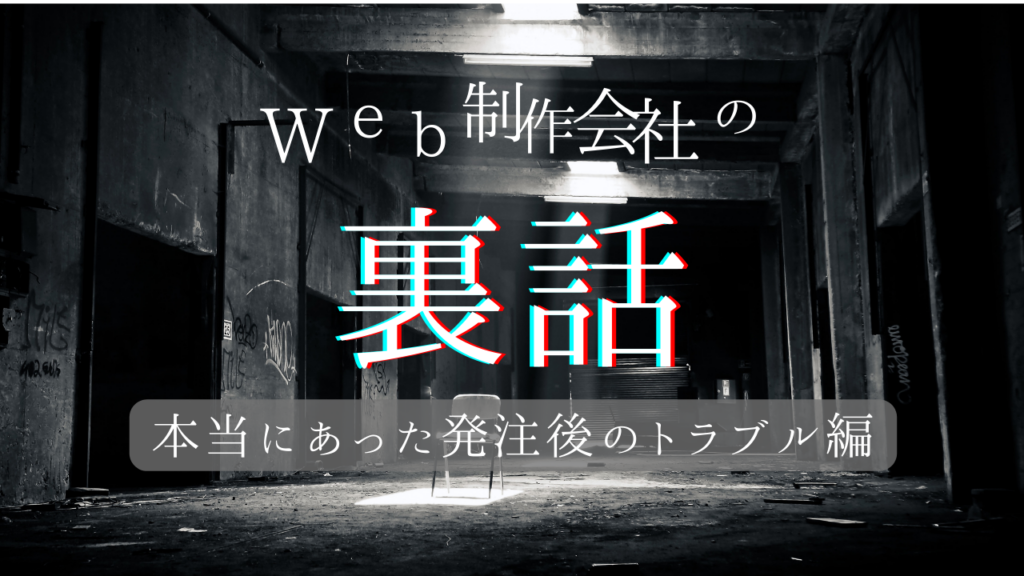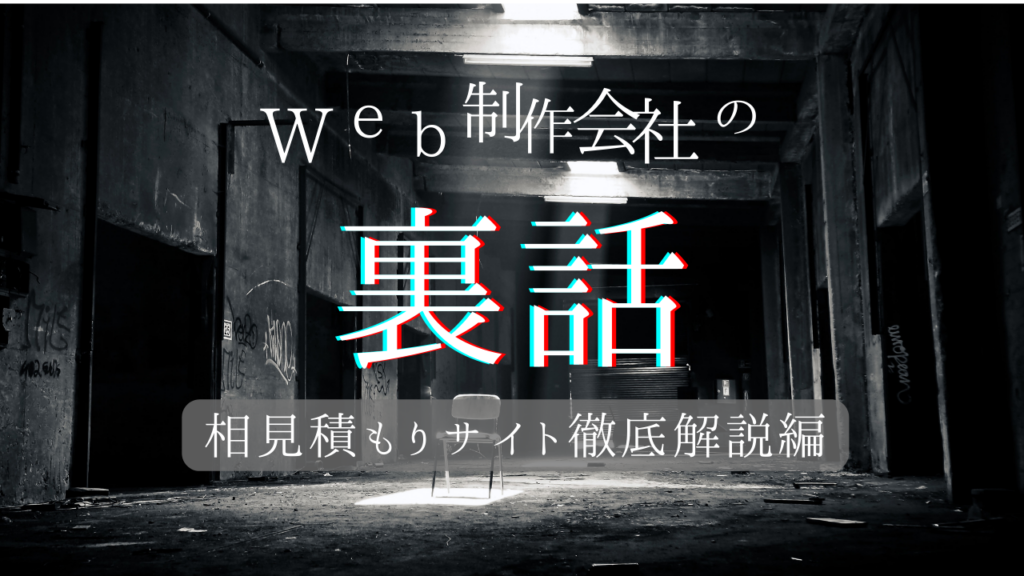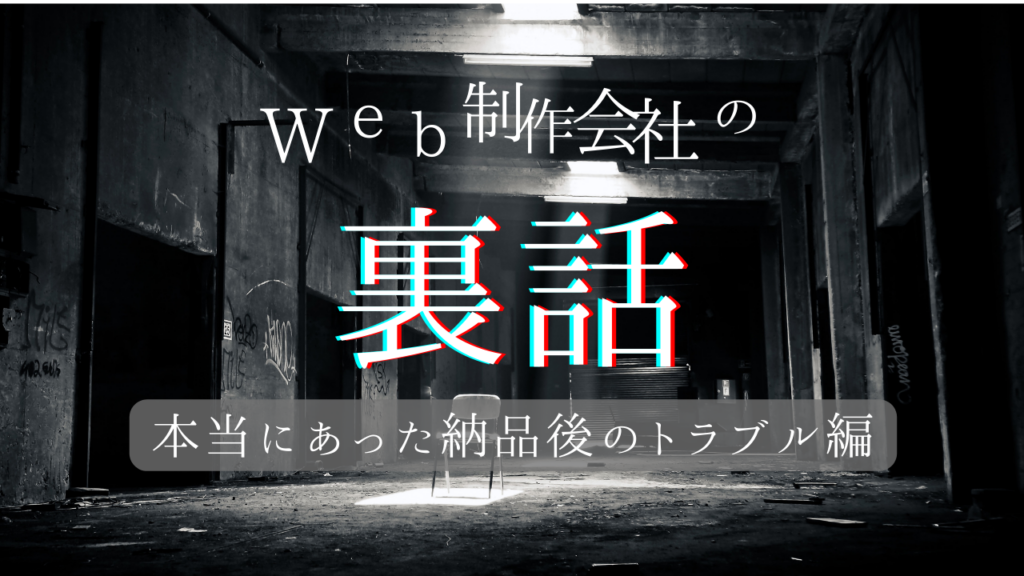
【本当にあったホームページ納品後のトラブル集】Web制作会社の裏話(2025年最新版)
ホームページ制作納品後にトラブルが起きないためには
ホームページを納品された後において、よく起こるトラブルはほとんどパターンが決まっています。
多くの人が似たような状況で同じ問題に陥りがちですが、これらの多くは事前に知っていれば回避できるものです。
ホームページ公開後の運営をスムーズに行うためには、このような回避可能なミスを避け、作業の負荷を減らして運営に集中できる環境を整えることが重要です。
今回の記事を読みことで、下記5つのよくあるトラブル集としてご紹介します。
①不完全な状態で納品させられ、請求を受けた
②公開後にバグや不具合が発生した
③「公開した」と言われたがGoogle検索しても自社サイトが引っかからない
④作ったホームページの権利は制作会社側にあると言われた
⑤成果が出ないことでトラブルになった
「本当にあのホームページ制作会社でいいのかしら?」
「見積書や発注書になかった金額を乗せて請求された」
「すでにトラブルが起きてしまって大変な目にあっている」
「ホームページは安く作ってもらって自社の売上拡大したい」
そんな方に向けてのお役立ちコラムとなっていますので、ぜひこの記事を最後までご覧ください。
|Webサイトが不完全な状態で強制納品させられた最悪なケース
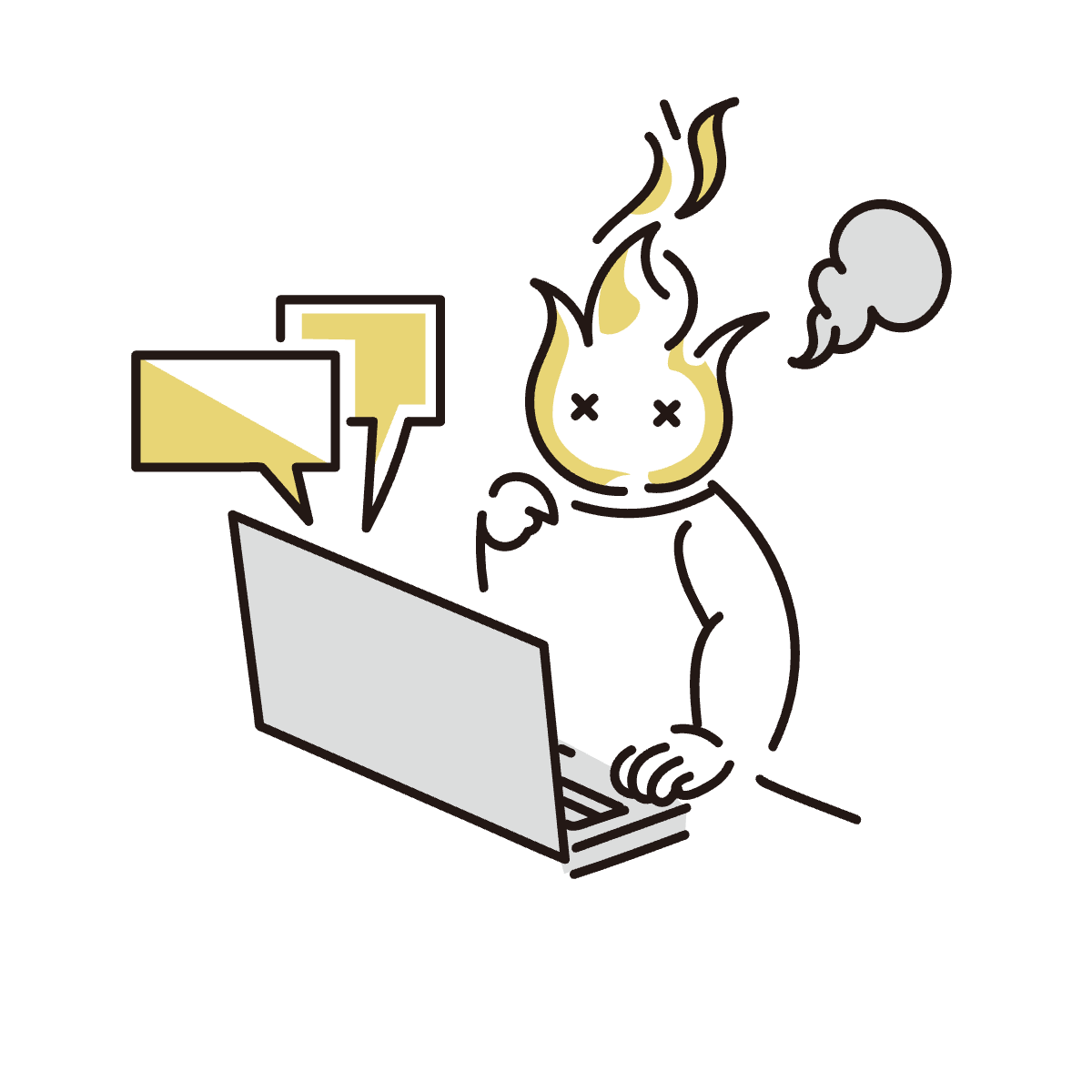
ホームページやシステム開発の納品は、本番サーバーへアップロードしたタイミングを”納品”とすることが一般的です。
しかし、Webサイトが不完全な状態で強制的に納品される最悪なケースも存在します。
1.納品前のテストがされていなかった
制作会社が納品期限に間に合わせるために、十分なテストを行わずに本番サーバーへアップロードする。
2. デザインが未完成
そもそもデザインの校了を出していない。
未完成の状態で納品(?)され、ページの一部が適切に表示されない、もしくは見栄えが悪い状況にあった。
3.コンテンツの不足
予定されていたコンテンツ(テキスト、画像、動画など)がすべて揃っていない状態で納品(?)された。
初期段階で要件が明確に定義されていないと、プロジェクトの途中で何度も要件が変更されることがあります。
また、制作会社が納期を絶対に守らなければならないというプレッシャーを感じると、品質よりもスケジュールを優先することがあります。
例えば、納期直前に大きなバグが見つかった場合でも、修正のための時間がないため、そのまま納品してしまうことがあります。
つらつらと書きましたがシンプルにお伝えすると、
この制作会社は、(無理やり)納品をして、発注側に制作費の請求をしたかったのでしょう。
|ホームページ公開後に発覚したバグや不具合はどうなる?(瑕疵担保期間)

瑕疵担保責任とは、ホームページに不具合が見つかった場合、制作会社が修理や補償を行う義務のことです。
民法上ではこの期間が1年とされていますが、
制作会社によっては3カ月や半年など、異なる期間が設定されていることもあります。
ページ数が少ないホームページであれば短い期間でも問題ないかもしれませんが、ECサイトやオウンドメディアなどシステム的な要素が含まれている場合は、できるだけ長い期間をお願いするのが望ましいです。
この点は少しわかりにくいかもしれませんが、「瑕疵担保責任の期間」は非常に重要なので、必ず確認するようにしましょう。
|制作会社「納品しました!」 あなた「Google検索しても出てこないけど何を言っているの?」
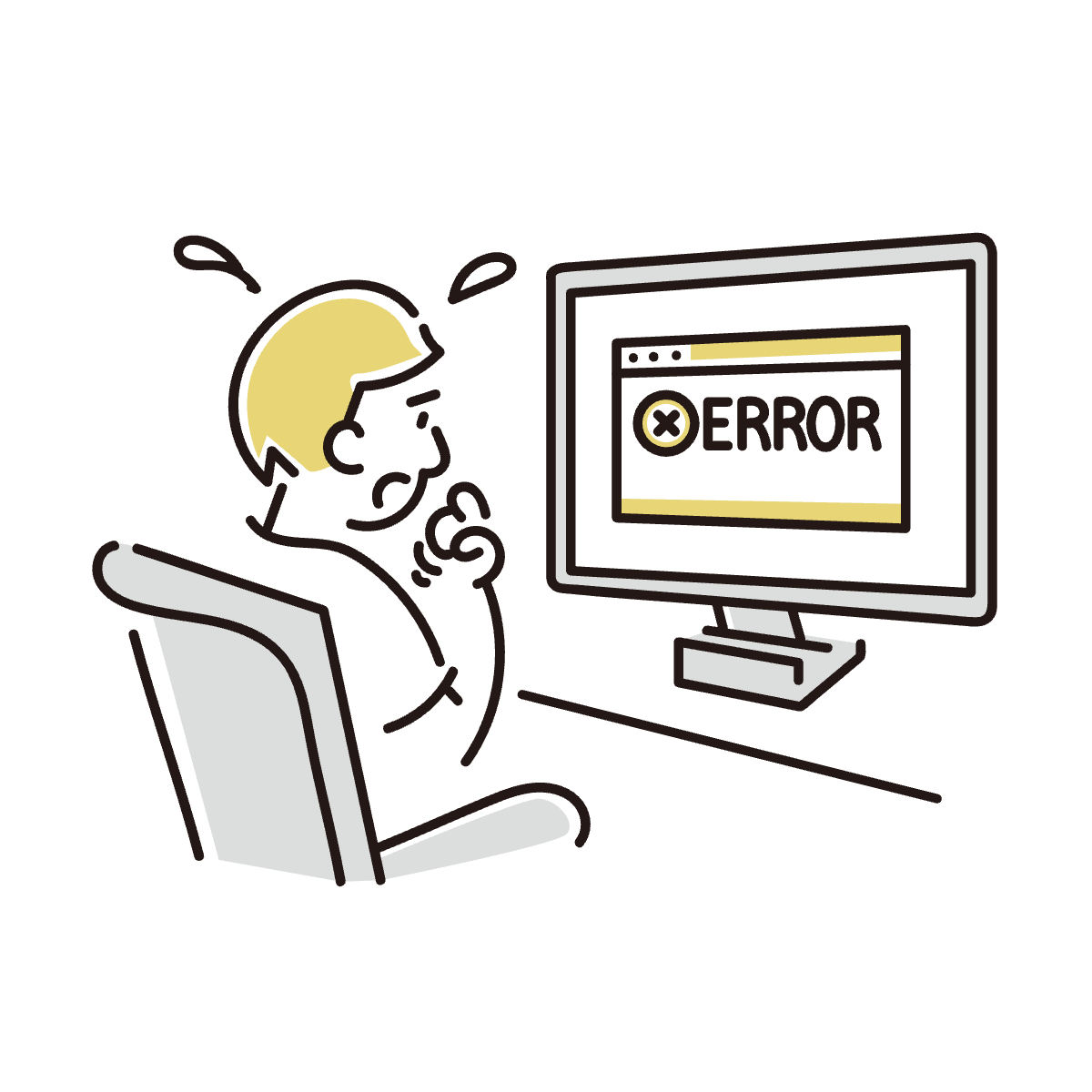
大丈夫です。安心してください。
全国1万社以上あるWeb制作会社で「公開の方法」を知らない会社はありません。
ここでは作業内容は割愛しますが、制作会社が「納品した」と言ったら全ての設定を行った上で本番サーバーには上がっている状態です。
新しいWebサイトは、公開後から検索にヒットするまでは、数日〜数週間待っていただく必要があります。
何故なのか?それは、”Googleの検索エンジンロボット”(所謂クローラー)が定期的に公開されているサイトを昼夜問わずに巡回してインデックス更新というものをしていきます。
ただし、公開されたすべてのサイトを瞬時に巡回することはできません。
これはGoogle側の仕様になるので、制作会社のせいにすることはできません。
とは言っても、「本当に公開されているのか?」と不安でしたよね。
でもこの情報を知ったあなたは、もう安心していますね。
大丈夫だと思いますので、もう少しお待ちいただければと思います。(制作会社目線で恐縮です。)
|納品後、「作ったホームページの権利は我々にある」と制作会社に言われた
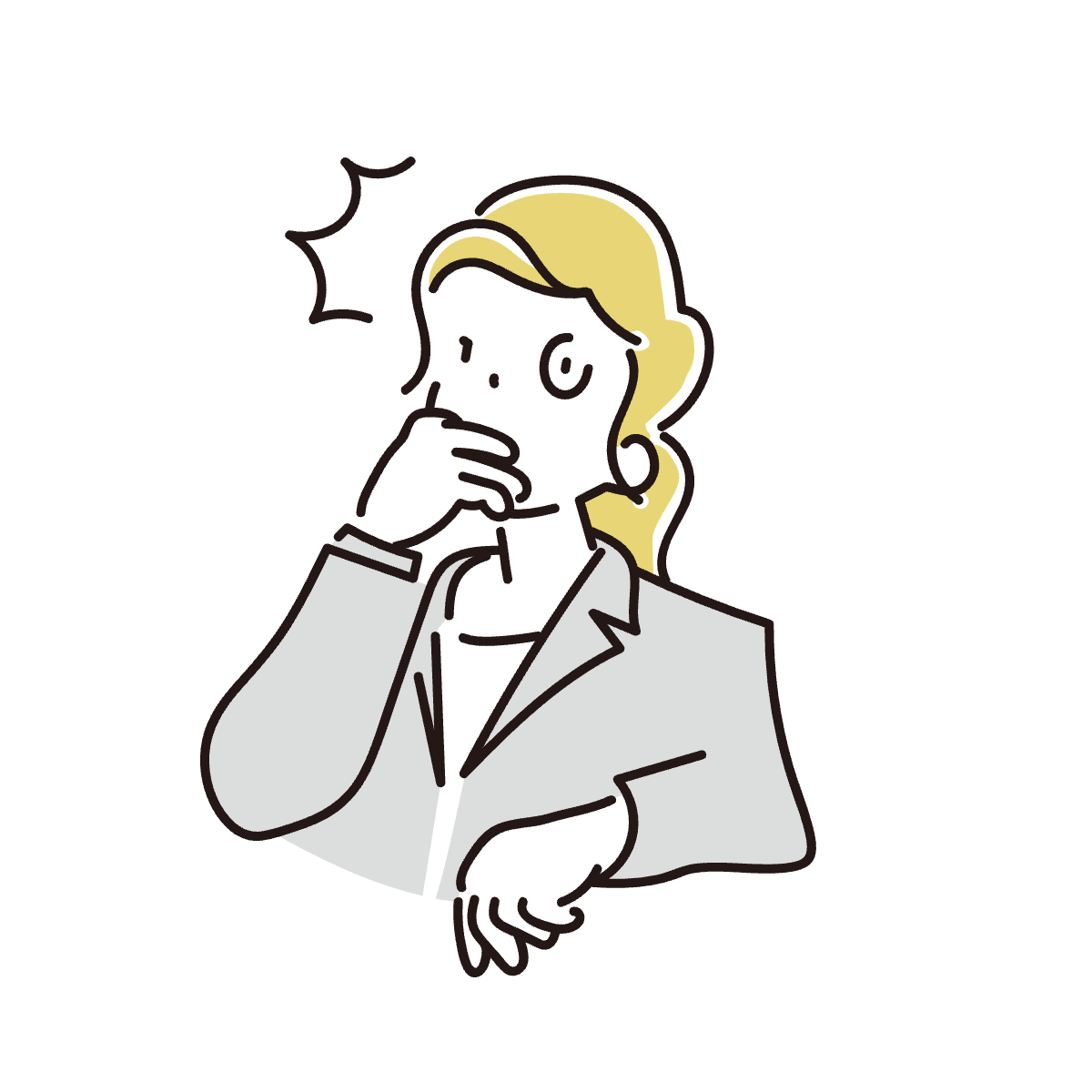
これは本当によくある事なので、注意が必要です。(裏話:契約前編でも記事が書かれてあります。)
あなた「私たちが依頼して作ってもらったから、私たちのものですよね?」
制作会社「いいえ、あなたが依頼してきたのは事実ですが、作ったのは我々なので著作権および所有権は我々にある」
一瞬「え?」となったと思いますが、”著作権および所有権”については契約前に気をつけていただきたいポイントの一つです。
そして、そういう話しなら他のホームページ制作会社に変更したい!
となったとしても「解約したらホームページは当社のものだ」「著作権は当社にあるので、情報を渡せない」と言われてしまうことがあります。
これに似たケースで、契約解除しようとすると数十万円の解除金が必要なケースがあったり、
解除するなら作ったWebサイトを消すなんていう悪徳Web制作会社もあります。(想像ではなく実際にあります。)
このような状況では、まるでホームページが”人質”のように扱われることになります。
大切なので再度になりますが、気を付けるべきポイントはただ一点で、契約前の打ち合わせで”著作権および所有権”の確認を必ず行うようにしてください。
|ホームページが公開された後、全く問い合わせや申込みがない?
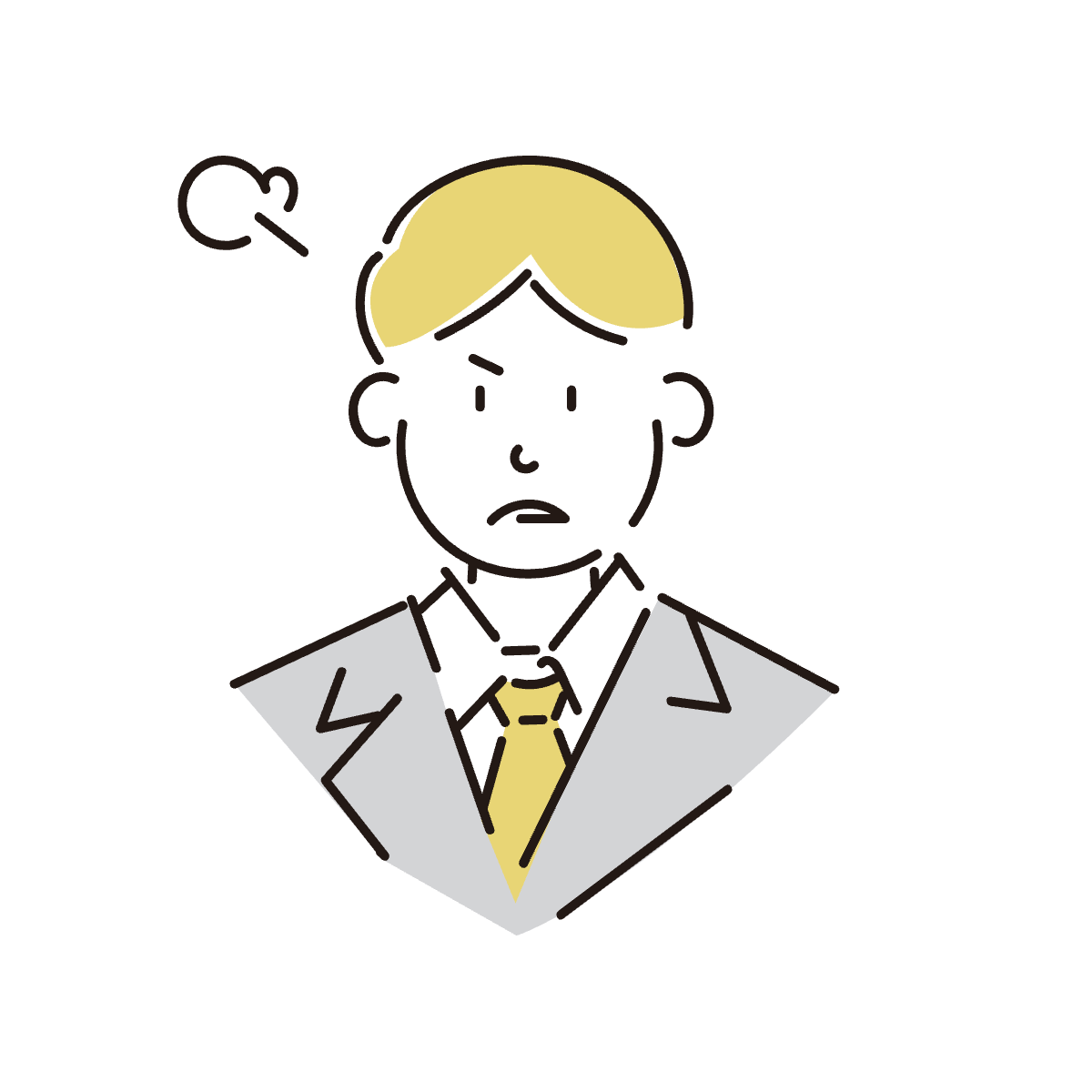
まず知っていただきたいのが世界で3億以上のアクティブWebサイトが存在しています。(動いてないWebサイトも含めると15億弱)
引用元:Total number of Websites – Internet Live Stats
日本だけで見ても1000万以上のサイトが存在する上で、例えエリアを狭めようと検索結果上位に引っ掛かることは稀であることを。
結論から言わせていただきます。
「特に何も考えずに、安くWebサイトを作っているから」です。
安くて良いWebサイトなど世の中に存在しません。
Web制作会社もどれだけ有名な会社であったとしても100発100中のクオリティを出せることはありえません。
他の競合他社はSEO対策やWeb広告などの「Webマーケティング」にあなたの想像以上の予算を使って戦っています。
その中で、数万、数十万円クラスで作ったWebサイトが勝てるわけがない。
はっきり言って諦めましょう・・・
100円でディナークルーズや、高級料亭の食事が出来ますか?という話しです。
100万円をお金をかけて作ったWebサイトですら泣かず飛ばずの時代です。
※理由は上記で述べている世の中のWebサイトの”数”が大きな要因となっています。
西暦2000年の時点では、およそ4000万(アクティブサイトは1700万)だったWebサイトが
今では15億(アクティブサイトは3億以上)だからです。
ちなみに、ホームページをリニューアルして「問い合わせが爆増した」というどこかにサイトの事例は紐解くと”ホームページが良かったから”ではなく、”元々のサービス内容が良かったから”という認識の方が正しいです。
とはいえ、ホームページは世の中に自社サービスを発信していくための”土台”ですので
より良い設計・デザインに越したことはないでしょう。
ただし、本気で自社売上拡大を狙うのであれば、ただサイト制作を量産してきた人に依頼するのではなく
以下3点の能力を持っている人がいるホームページ制作会社に依頼するべきです。
①あなたのビジネスを理解できて、自分ごとのように本気で取り組んでくれる人
②そのビジネスのターゲティングができて、それぞれのターゲティングに対して個別のメッセージングを考えられる人
③それぞれのターゲティングに対して個別のメッセージングを考えられる人
これらのマーケティング能力がある人に出会えれば、あなたのビジネスはきっとうまくいきます。(私はそれを実際に見てきました。)
表題の回答に戻りますが、〈問い合わせや申込み=売上を上げるため〉のホームページ制作なのであれば
絶対的に作って終わりではないので、作った後のことも一緒に考えてくれる担当者に出会えることを望んでいます。
では、そういった能力を持っている人にどうやったら出会えるのか?
その提供の場がチョコミツになっています。
(まとめ)Web制作会社の裏話 納品後編
最終的にかなり激しい記事になってしまって、自分でも驚いています。
Webサイト制作におけるトラブルや誤解を防ぐためには、依頼する前にWebサイトの役割を明確にすることが大切です。
単に存在感を示すためだけにサイトが欲しい場合は、安価な制作でも問題ありません。
しかし、売上拡大を狙いたいのであれば、安価な選択は避けるべきです。
安価なWebサイトでは、競合他社と同じようなレベルのSEO対策やWebマーケティングが期待できないため、結果的に効果が薄い可能性が高くなりがちなのはご理解いただけたかと思います。
納品後のトラブルを避けるために、事前に確認しておかないといけないことが多くありますが、それらをしっかりと把握することで、後々の問題を未然に防ぐことができます。
まず、見積書や契約書の内容を詳細に確認し、作業範囲や納品物の仕様を明確にしておくことが重要です。
特に追加作業や修正に関する取り決め、対応可能なブラウザやデバイス、サーバーやドメインの設定など、具体的な要件をしっかりと確認しておきましょう。
また、納期についてはホームページ制作会社と取り決めた日付が明確に定められているか、遅延が発生した場合の対応策が記載されているかを確認することで、納品遅延によるトラブルを極力避けることができます。
納品後についてはサポート体制についても確認しておきましょう。
瑕疵担保責任の期間や範囲を把握し、不具合が発生した際の対応方法を事前に確認しておくことが大切です。
最後に、コミュニケーションの取り方も事前に確認しておくべきです。
定期的な進捗報告やミーティングのスケジュールを設定し、常にプロジェクトの進行状況を把握することで、予期せぬトラブルを防ぐことができます。
これらの事前確認を徹底することで、納品後のトラブルを避け、スムーズなホームページ運営を実現することができます。
この記事は長くなりましたが、一読いただき誠にありがとうございました。

年代:20代
キャリア:都内の某大学法学部を卒業後に広告代理店でコピーライターとして7年間勤務した後、 Webライターに転身。現在はチョコミツ調査部メインで活動中。