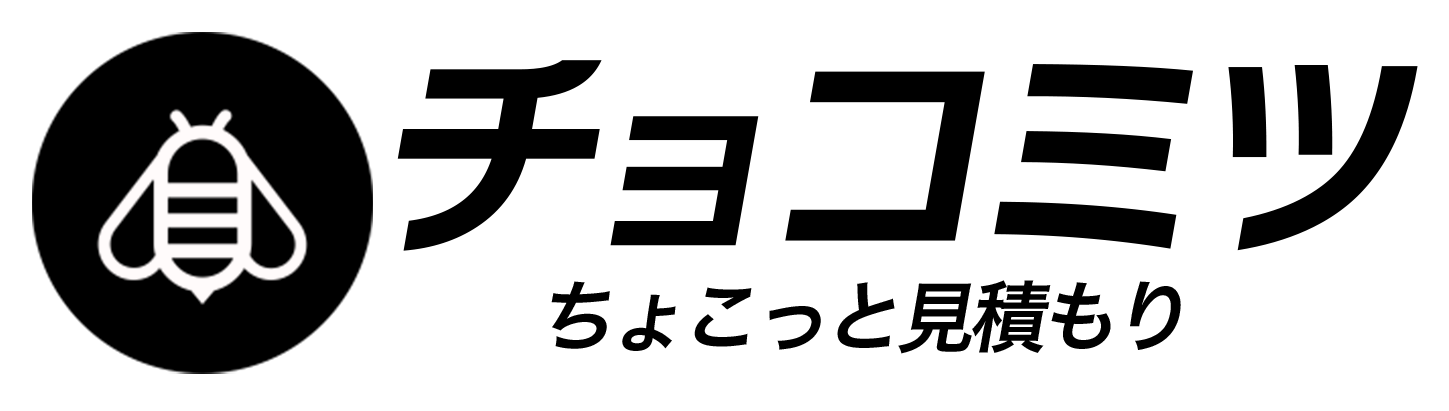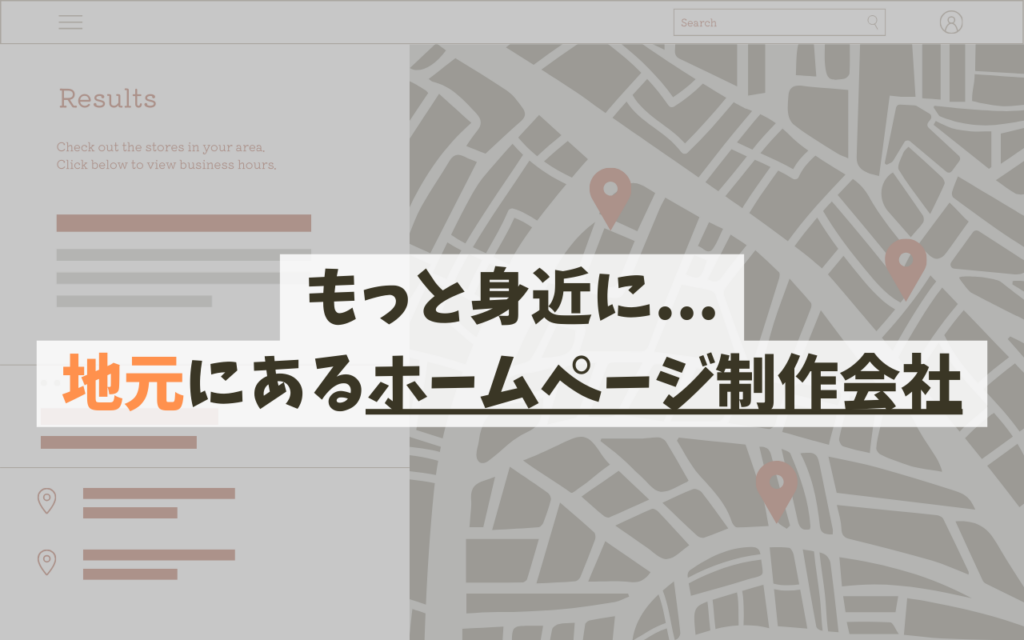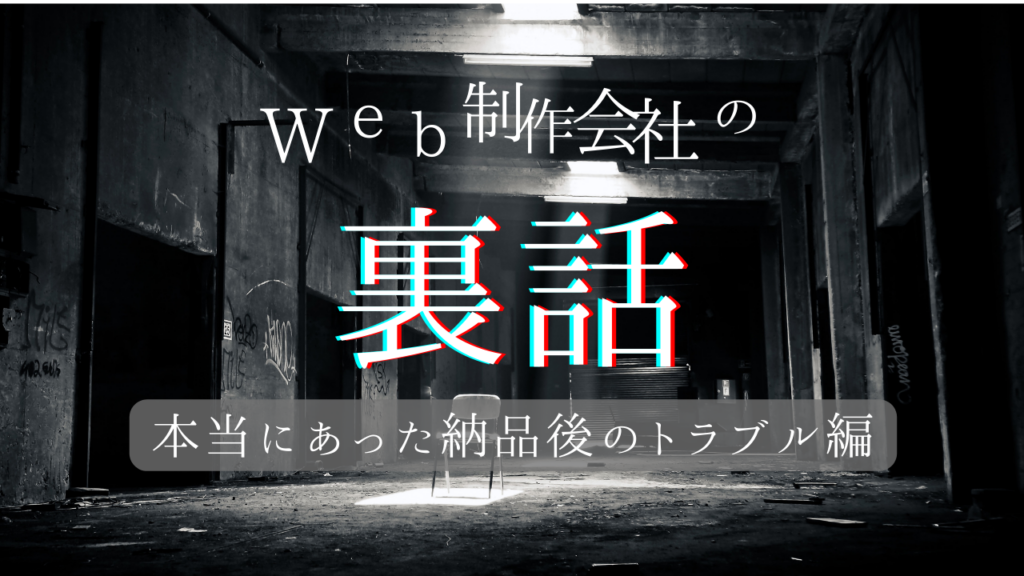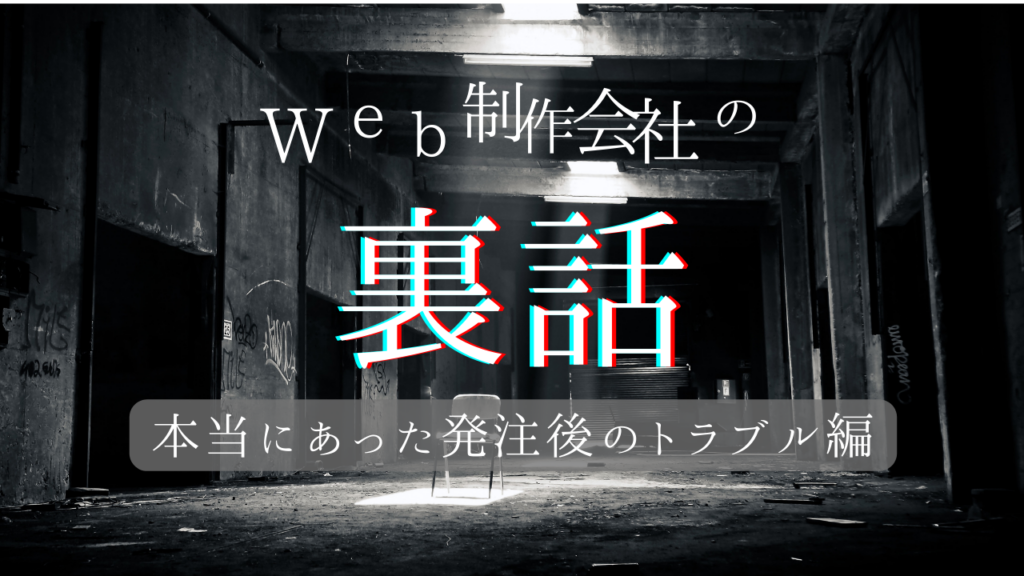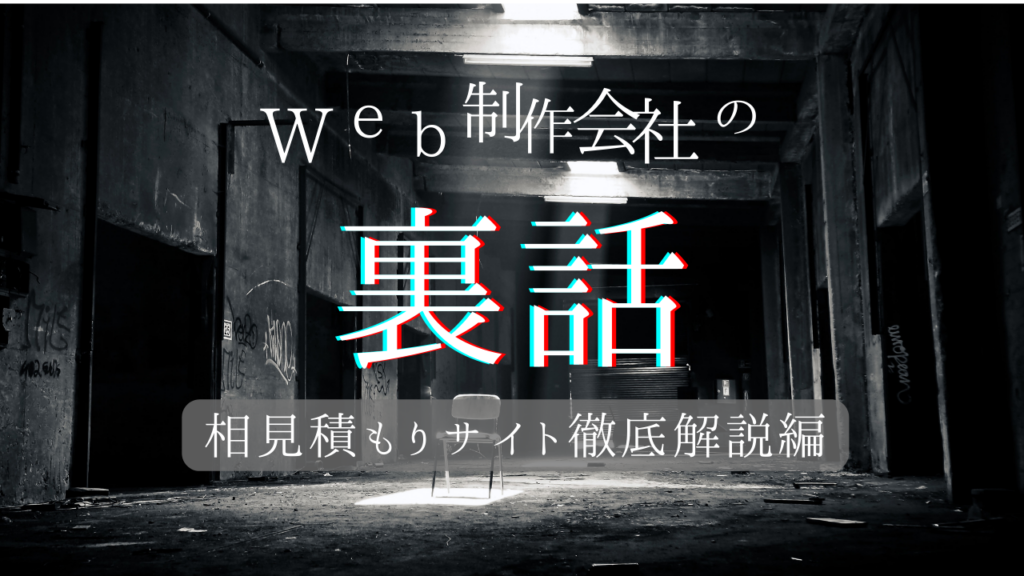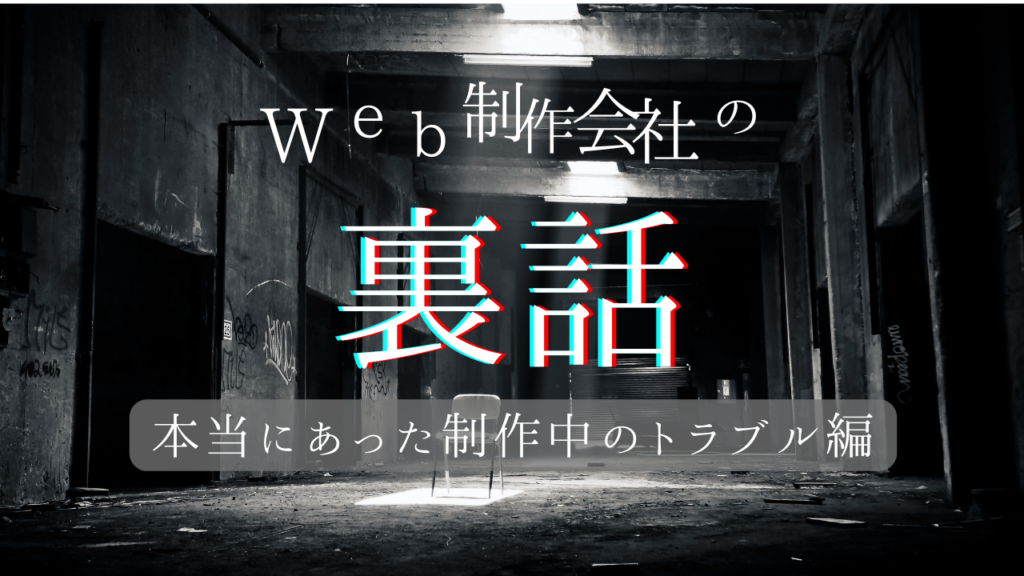
【本当にあったホームページ制作中のトラブル集】Web制作会社の裏話(2025年最新版)
ホームページ制作途中にトラブルが起きないためには
ホームページの制作依頼中において、よく起こるトラブルはほとんどパターンが決まっています。
多くの人が似たような状況で同じ問題に陥りがちですが、これらの多くは事前に知っていれば回避できたものです。
ホームページ制作の進行をスムーズに行うためには、このような回避可能なミスを避け、作業の負荷を減らしてコンテンツ作成に集中できる環境を整えることが重要です。
今回の記事を読みことで、下記6つのよくあるトラブル集としてご紹介します。
①希望したデザインになっていない
②ブラウザによって表示が異なっている
③スマホでもPC用画面で表示されて見にくい
④追加費用を請求される
⑤期日に納品されない
⑥修正に応じてくれない
「トラブルって未然に防げるのかな?」
「すでにトラブルが起きてしまって大変な目にあっている」
そんな方に向けてのお役立ちコラムとなっていますので、ぜひこの記事を最後までご覧ください。
|要望無視?全くイメージしていなかったデザインが上がってきた
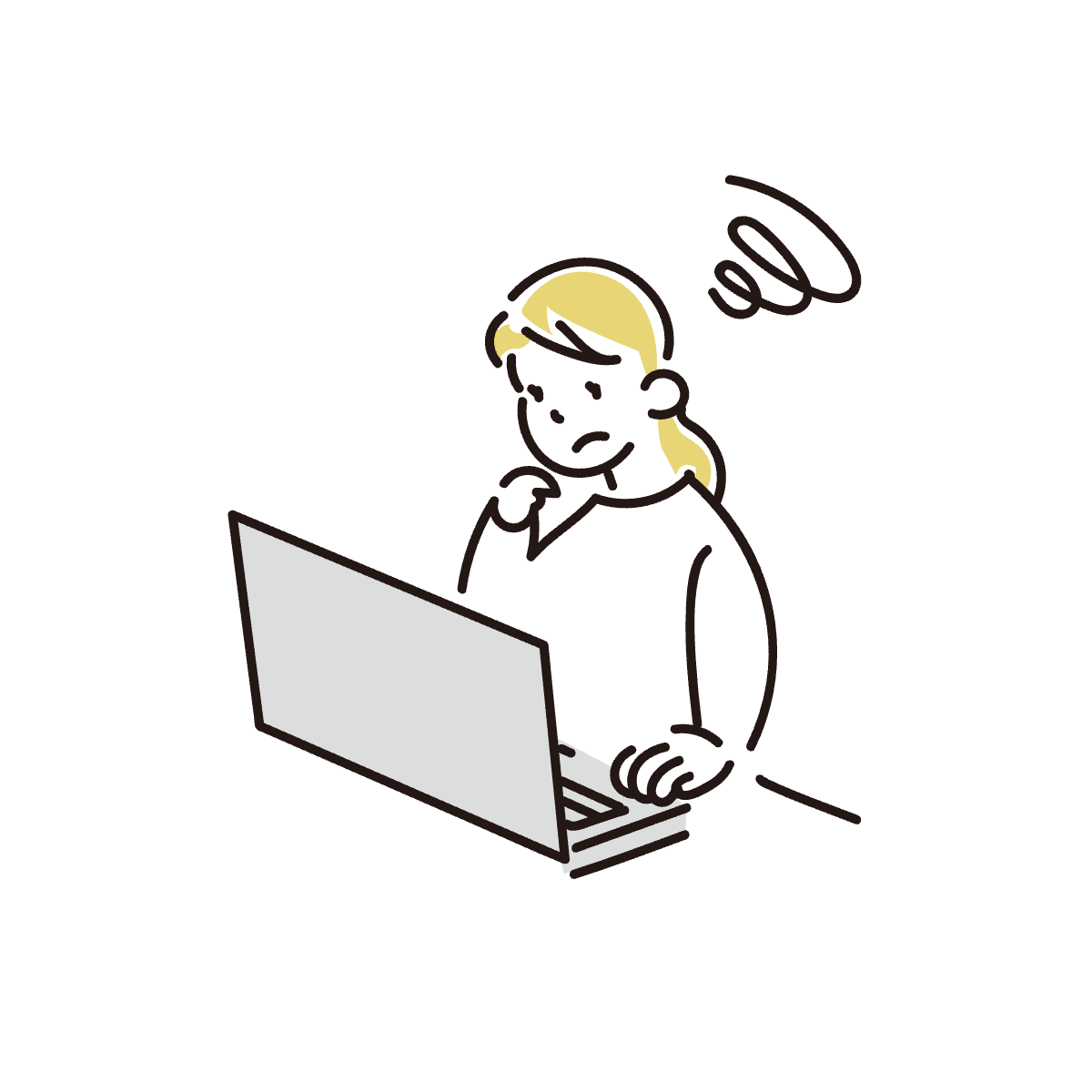
ホームページ制作のデザイントラブル?
ホームページ制作における最も多いトラブルの一つが、デザインに関するものです。多くのデザイントラブルは、依頼者と制作会社のコミュニケーション不足が原因で起こります。
〈原因〉
1.コミュニケーション不足
依頼者が自分の希望やイメージを十分に伝えず、制作会社が理解できないままデザインを進めてしまう。
制作会社が詳細なフィードバックを求めずに進行し、依頼者の期待に応えられない結果になる。
2.不明確な要望
依頼者が具体的なデザインのイメージを持っていない、または具体的な要望を伝えられないため、制作会社がどの方向性でデザインを進めるべきかわからなくなる。
3.期待の相違
依頼者と制作会社の間で、デザインに対する期待や基準が異なり、最終的に満足のいくデザインができない。
〈改善できるポイント〉
1.具体的なイメージと要望を伝える
デザインを制作会社に丸投げせず、自分の希望するデザインのイメージや要望をしっかりと伝えましょう。
参考になるホームページやデザインを複数提示することで、具体的なイメージを共有できます。
2.緻密な打ち合わせを行う
自社の目的にあったデザインにしてもらうためには、納得いくまで制作会社と打ち合わせを行いましょう。定期的なミーティングやレビューを行うことで、進行状況を確認し、必要な修正を早期に行えます。
3.プロトタイプの確認
制作会社が提供するテストサイトのことを指します。
本番サーバーへアップしてしまうと、Google検索に引っ掛かり、中途半端なホームページが表示されてしまうので、テストサイトで初期デザインをしっかり確認し、フィードバックを提供することで、最終的なデザインの品質を高めることができます。
4.明確なデザインブリーフ(見た目の設計)を作成
依頼者と制作会社が共通の理解を持つために、明確なデザインブリーフを作成しましょう。
ブリーフには、デザインの目的、ターゲットオーディエンス、主要なメッセージ、必須要素などを具体的に記載します。
5.オープンなコミュニケーション
双方が自由に意見を交換できるオープンなコミュニケーションを心掛けましょう。依頼者は自分の意見を率直に伝え、制作会社は依頼者のフィードバックを積極的に取り入れることが重要です。
正直、より良いWebサイトを作る上でこれが一番重要です。
お互い警戒せずに伝えないといけないことは必ず伝えていきましょう。
デザインのトラブルを防ぐためには、依頼者と制作会社の間でしっかりとしたコミュニケーションを取ることが不可欠です。
具体的なイメージや要望を伝え、綿密な打ち合わせを行い、プロトタイプの確認を怠らず、明確なデザインブリーフを作成することで、トラブルを避け、自社の目的に合ったデザインを実現することができます。
|見え方が違う(Google Chrome、Microsoft edge、Safari)

ホームページ制作において、異なるデバイスやブラウザでの表示に関するトラブルは非常に一般的です。具体的には、ブラウザやデバイスによってホームページの見え方が異なり、そのサイトを利用するユーザー体験(UX)に悪影響を及ぼすことがあります。
〈原因〉
1.ブラウザの違い
Google Chrome、Safari、Firefox、Edgeなど、様々なブラウザが存在し、それぞれのブラウザでHTMLやCSSの解釈が異なるため、同じホームページが異なって表示されることがあります。
2.ブラウザのバージョン
各ブラウザには複数のバージョンがあり、古いバージョンでは最新のウェブ技術に対応していないため、ホームページの表示が崩れる可能性があります。
3.レスポンシブデザインの欠如
モバイルデバイス、タブレット、デスクトップなど、異なる画面サイズや解像度に対応するレスポンシブデザインが適切に実装されていない場合、表示が崩れることがあります。
4.ブラウザの互換性テストの不足
制作会社が十分なブラウザ互換性テストを行わず、主要なブラウザ以外での表示確認を怠ると、ユーザーが使用しているブラウザで問題が発生する可能性があります。
〈改善できるポイント〉
1.対応ブラウザの確認
制作会社が対応するブラウザを事前に確認し、契約書に明記してもらいましょう。
多くの制作会社では「Google ChromeやSafariの最新バージョンのみ対応」といった条件があります。
契約前に対応ブラウザを確認することで、後から追加費用が発生するリスクを避けられます。
2.ブラウザ互換性のテスト
制作段階で、主要なブラウザやそのバージョンでの表示確認を徹底しましょう。特に、Google Chrome、Safari、Firefox、Edgeなどの主要ブラウザでの表示確認を行うことが重要です。
3.レスポンシブデザインの実装
モバイル、タブレット、デスクトップなど、さまざまなデバイスでの表示に対応するレスポンシブデザインを実装します。これにより、画面サイズや解像度に応じて自動的にレイアウトが調整されるため、どのデバイスでも適切に表示されます。
4.追加費用のリスク回避
契約前に、どのブラウザまで対応するのかを明確にし、それ以外のブラウザに対応する場合の追加費用についても確認しておきましょう。契約時に詳細な条件を把握することで、予期しない追加費用の発生を防ぐことができます。
5.継続的なメンテナンス
ホームページの運用後も、ブラウザのアップデートや新しいデバイスの登場に伴い、定期的なメンテナンスを行うことで、常に適切な表示を維持することができます。
ブラウザやデバイスによる表示の違いは、ホームページ制作における一般的なトラブルの一つです。
これらの問題を防ぐためには、対応ブラウザの確認、ブラウザ互換性テストの実施、レスポンシブデザインの実装、追加費用のリスク回避、そして継続的なメンテナンスが重要です。
これらのポイントを押さえることで、全てのユーザーに対して不信感のない安全なWebサイトを提供することができます。
|今の時代はスマホ対応は必須!レスポンシブ対応とは?
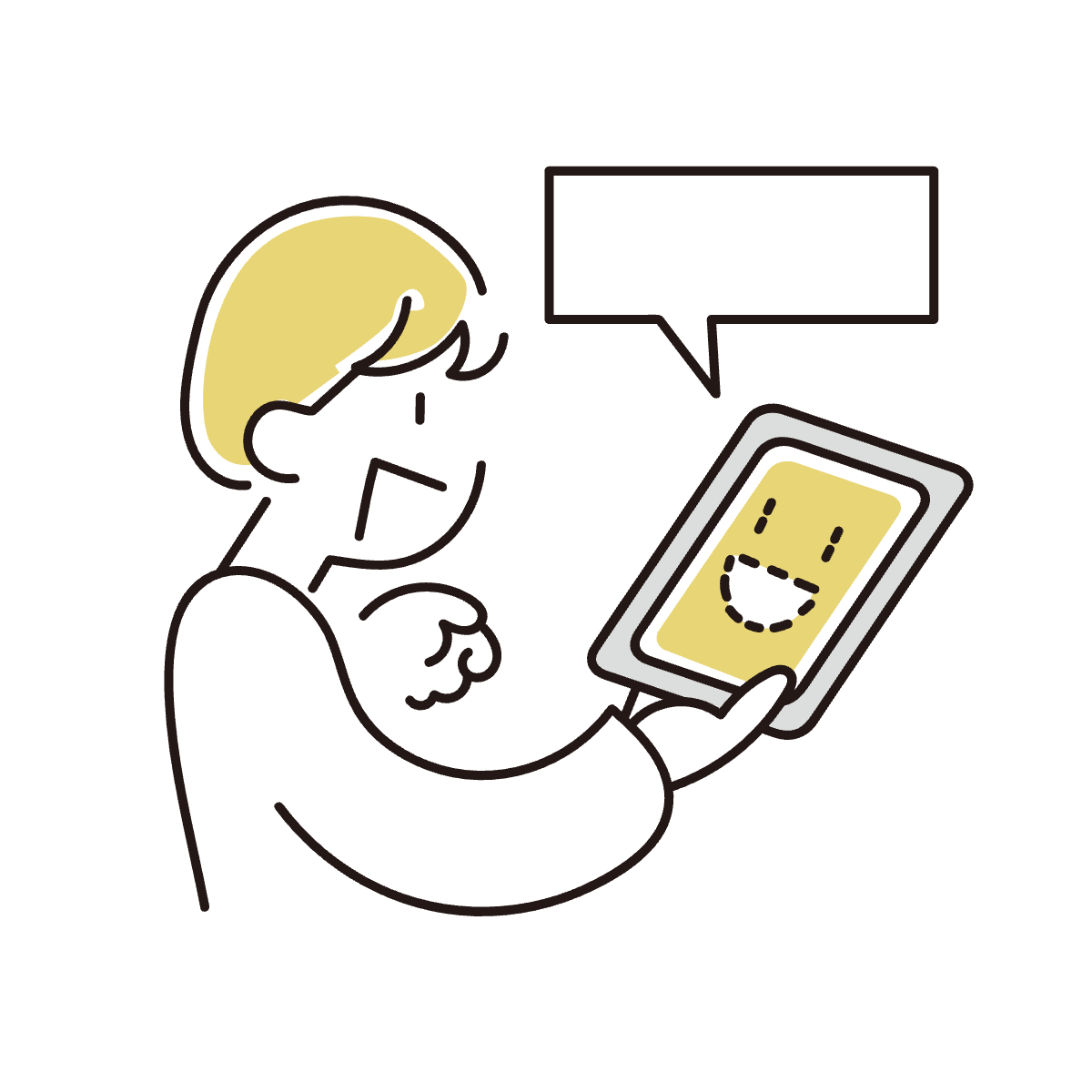
現代では、PCよりもスマートフォンでホームページやWebサイトを閲覧するユーザーが増えています。にもかかわらず、PC用に設計されたホームページをそのままスマホで見ると、画面が圧縮されて見づらく、ユーザーがサイトを離れてしまうことがよくあります。
この問題を解決するためには、レスポンシブデザインの導入が重要です。
〈原因〉
1.PC専用のデザイン
PC用にデザインされたホームページは、大きな画面サイズを前提としているため、スマホで閲覧すると内容が圧縮され、レイアウトが崩れることがあります。
2.レスポンシブデザインの未対応
スマホでの閲覧に対応していないデザインでは、画面サイズに合わせたレイアウト調整が行われず、表示が適切に行われません。
3.制作会社の方針
一部の制作会社では、レスポンシブデザインを基本料金に含めていない場合があり、別途オプション料金が発生することがあります。
4.ブラウザの互換性テストの不足
制作会社が十分なブラウザ互換性テストを行わず、主要なブラウザ以外での表示確認を怠ると、ユーザーが使用しているブラウザで問題が発生する可能性があります。
〈改善できるポイント〉
1.レスポンシブデザインの導入
レスポンシブデザインを採用することで、PC用のホームページがスマホやタブレットなど異なる画面サイズに自動的に最適化され、ユーザーにとって使いやすい表示が可能になります。
レスポンシブデザインは、画面サイズに応じてレイアウトやコンテンツの表示を調整する技術です。
2.制作会社との事前確認
ホームページ制作を依頼する前に、レスポンシブデザインが基本料金に含まれているか、またはオプション料金として別途請求されるのかを明確に確認しておきましょう。契約前に詳細を確認することで、後から追加費用が発生するトラブルを避けられます。
3.モバイルファーストのアプローチ
可能であれば、スマホ向けのデザインを最初に考え、その後PC用のデザインを組み合わせる「モバイルファースト」のアプローチを採用しましょう。
これにより、スマホでのユーザー体験を最優先にしながら、PC用にも最適化されたデザインが実現できます。
4.テストとフィードバックの徹底
制作過程で、様々なデバイスやブラウザでの表示確認を行いましょう。
スマホやタブレットでの実際の表示を確認し、必要に応じて修正を加えることで、ユーザーにとって快適な閲覧体験を提供できます。
5.ユーザビリティの向上
スマホでの操作性を向上させるために、タップしやすいボタンやリンク、適切なフォントサイズ、読みやすいレイアウトを心掛けましょう。
これにより、スマホユーザーの利便性が高まり、サイトの離脱率を低く抑えることができます。
PC用にデザインされたホームページがスマホで見づらくなる問題は、レスポンシブデザインを導入することで解決できます。
レスポンシブデザインを基本料金に含む制作会社を選ぶか、オプション料金について事前に確認し、モバイルファーストのアプローチやテスト、ユーザビリティの向上に取り組むことで、全てのデバイスで快適に閲覧できるホームページを実現しましょう。
|「そんなの最初に聞いてない!」予想外の追加費用?
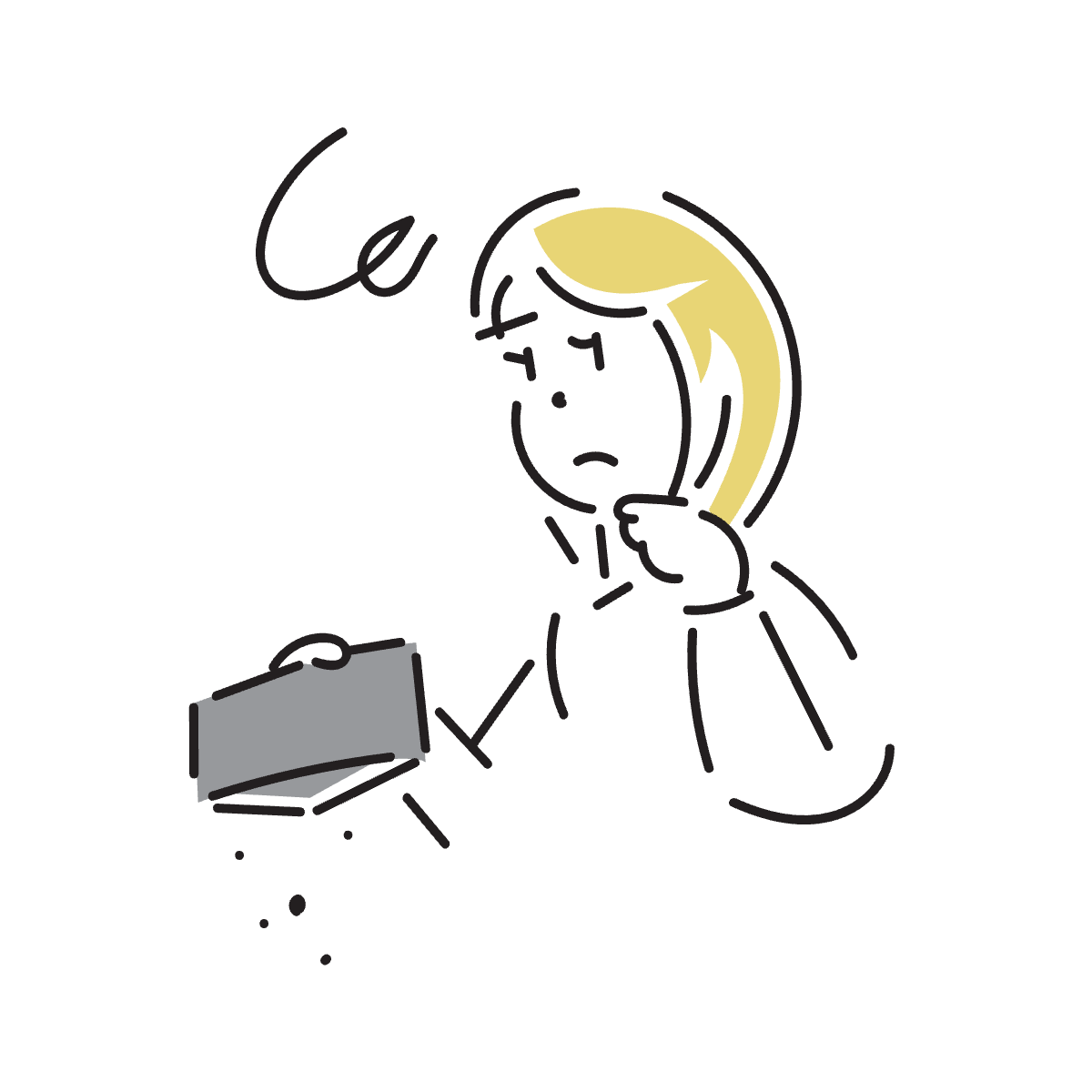
ホームページ制作において、追加費用の請求はよくあるトラブルの一つです。
主に、契約書の内容を確認していなかったことや、プロジェクトの進行中に発生する追加作業により、予想外の費用が発生することがあります。
これを防ぐためには、事前の確認と明確なコミュニケーションが重要です。
〈原因〉
1.契約書の確認不足
契約書に記載されている内容や条件を十分に確認せずに契約を進めてしまうと、後から想定外の追加費用を請求される可能性があります。
2.追加作業の発生
プロジェクトの進行中に追加作業が発生することがあります。
例えば、スマホ表示への対応、追加コンテンツの作成、サーバーやドメインの設定などが追加費用を引き起こす原因です。
3.不明瞭な作業範囲
作業内容や責任範囲が契約書に明記されていない場合、制作会社が追加作業を行い、その分の費用を追加請求するケースがあります。
〈改善できるポイント〉
1.契約内容の詳細確認
ホームページ制作を依頼する前に、契約書に記載されている内容を十分に確認しましょう。
特に、費用に関する項目、作業範囲、追加作業に関する規定などをしっかりと把握しておくことが大切です。
2.明確な作業範囲の定義
契約書において、作業範囲や責任範囲を詳細に定義してもらうことが重要です。
例えば、どこまでが基本料金に含まれるのか、追加作業が発生した場合の費用について明記してもらうと良いでしょう。
3.追加作業の確認と合意
プロジェクトの進行中に追加作業が必要となった場合は、必ず事前に制作会社から連絡を受け、その追加費用について合意するようにしましょう。追加作業が発生する場合の手順を契約書に盛り込むことも有効です。
4.予算超過の事前通知
制作が開始された後、予算を超えそうな場合は、必ず制作会社にその旨を伝え、追加費用が発生する場合の対応策を話し合うことが重要です。
予算内での対応が難しい場合は、追加費用についての詳細な説明を求めましょう。
5.サーバー・ドメインの設定の確認
サーバーやドメインの設定が含まれているか、追加費用が発生するのかを確認しておくことも重要です。これらの費用が含まれていない場合、別途費用が発生することがあります。
もし仮に、この部分を無償で対応してもらえる企業があったら、四葉のクローバーを見つけたことと同意義と捉えていいと思います。(私の主観)
6.コンテンツ作成の範囲の確認
画像やテキストの作成、校正などのコンテンツ作成が含まれているかどうかを事前に確認しましょう。
制作会社がコンテンツを全て作成する場合、追加費用が発生することがありますので、その点も契約前に確認しておきましょう。
ホームページ制作における追加費用のトラブルを回避するためには、契約書の詳細な確認と、作業範囲の明確な定義が不可欠です。追加作業が発生した場合は、必ず事前に連絡を受け、その費用について合意することが重要です。また、サーバーやドメインの設定、コンテンツ作成の範囲についても確認しておくことで、予期しない費用の発生を防ぐことができます。
|「いい加減これ以上の遅延は許されない!」予想外の追加費用?
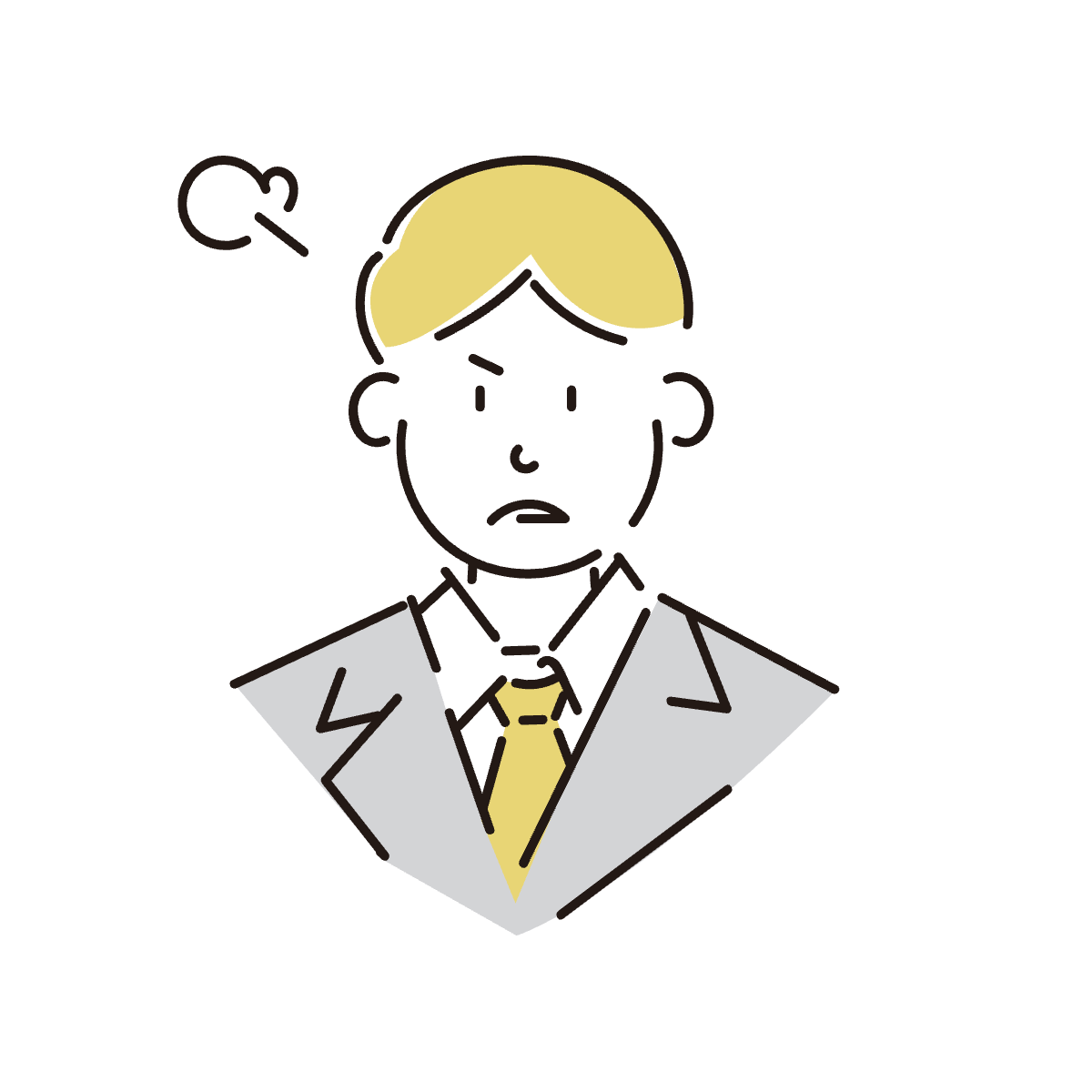
ホームページ制作において、期日に納品されない、または遅延するトラブルは非常に困る問題の一つです。
特に、納期通りにホームページを公開できないと、元々予定していたビジネスのスケジュールに大きな影響を及ぼすことがあります。
以下では、納期遅延の原因と改善できるポイントを詳しく説明します。
〈原因〉
1.契約内容や作業内容の変更
契約後に追加作業を依頼したり、契約内容を変更することで、制作スケジュールが遅れる原因になります。
追加作業や変更があると、その分の時間が必要になるため、納期に影響を及ぼすことがあります。
2.コミュニケーション不足
制作過程でのコミュニケーション不足や、情報共有が不十分であると、進行が遅れることがあります。
全体のスケジュールに間に合わせるのではなく、制作工程ごとに細かい予定を共有しなければ、納期に間に合わないことが多いです。
3.プロジェクト管理の不備
一言で言うと「担当ディレクターの管理不足」です。
つまりその人を選んだ発注者側の選択責任も多少入ってきます。
ホームページ制作会社を選定する上で、会社で選ぶのではなく、担当者で決めた方がいい理由はこの部分が大きく占めます。
担当ディレクターの経験が多ければより良いとされますが、40歳以上の担当になると”イマドキ”に疎くなるため20代後半〜30代前半の担当者を選ぶのがベストとなっています。
〈改善できるポイント〉
1.契約前の詳細な打ち合わせ
契約前、つまり見積もり段階から制作スケジュールや納期に関する詳細をしっかりと打ち合わせておきましょう。
どの段階で何を行うのか、スケジュールを明確にしておくことが重要です。
これにより、制作プロセスがスムーズに進みます。
2.追加作業や変更の管理
契約後に追加作業や変更が発生する可能性がある場合は、その際にどのように納期に影響を与えるかを事前に確認し、追加費用やスケジュールの見直しについても合意しておくことが大切です。
追加作業や変更がある場合は、納期が遅れる可能性があることを理解しておきましょう。
3.進捗確認と報告の徹底
制作が進行している間、定期的に進捗状況を確認し、制作会社からの報告を受けるようにしましょう。
1〜2週間に一度進捗状況を把握することで、遅延が発生する前に対策を講じることができます。
ホームページ制作における納期遅延を防ぐためには、信頼できる制作会社の選定、契約前の詳細な打ち合わせ、追加作業や変更の管理、進捗確認と報告の徹底、契約書に納期に関する条項を明記することが大切です。
また、”しっかり対応してくれる優秀なWebディレクター”がいる会社の剪定をした上で、制作過程でのコミュニケーションを徹底することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズなプロジェクト進行を実現しましょう。
|「デザインを何回もやり直し・・・」終わらない案件への入口へ
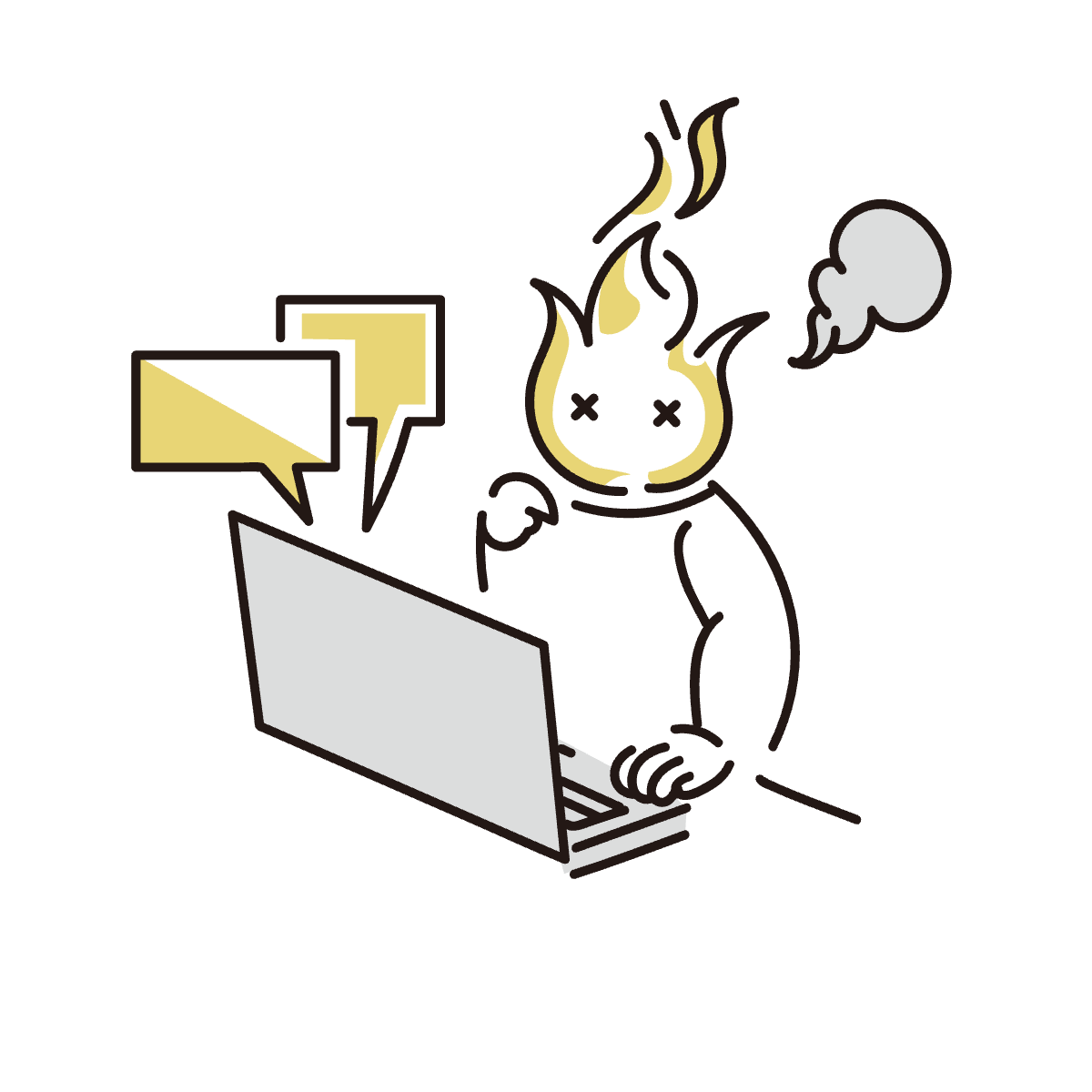
ホームページ制作のプロジェクトでは、デザインの修正に関するトラブルがよく発生します。
特に、修正に応じてもらえない、あるいは修正において追加費用が発生する場合があります。
以下にその原因と改善ポイントを詳しく解説します。
〈原因〉
1.修正回数の制限
一般的に、デザインの修正回数はホームページ制作の基本料金に含まれており、事前に定められた回数の修正しか含まれていない場合が多いです。
例えば、トップページの修正回数が3回、下層ページが2回までなど、制作会社や契約内容によって異なります。
2.コーディング完了後の修正
HTMLやCSSでのコーディングが完了した後のデザイン修正は、技術的に大きな手間がかかるため、追加費用が発生することが多いです。
特に、デザインの大幅な変更は、コーディングのやり直しが必要になり、追加の作業が伴います。
3.契約前の確認不足
修正に関する契約内容を十分に確認していないと、後から修正ができない、または追加費用が発生するなどのトラブルが生じることがあります。
4.コミュニケーション不足
制作過程でのコミュニケーション不足により、デザインのイメージや要望が正確に伝わらず、修正が多くなってしまうことがあります。
これにより、契約で定められた修正回数を超えてしまうことがあります。
〈改善できるポイント〉
1.契修正回数の明確化
契約前に、デザイン修正の回数や範囲について詳細に確認しておきましょう。
例えば、「トップページの修正は3回まで」「下層ページは2回まで」といった具体的な回数を明記してもらうことが大切です。
2.コーディング前のデザイン確認
コーディング作業に入る前に、デザインの最終確認を行いましょう。
デザインが確定する前に修正をしっかり行うことで、コーディング後の修正を最小限に抑えることができます。
デザインが完成してからコーディングに入る前に、全ての要望や修正点を反映させるようにしましょう。
3.修正の必要性を最小限にする
デザインの段階で、できるだけ具体的な要望を制作会社に伝え、詳細なデザイン案を事前に確認することで、後からの修正が少なくて済むようにしましょう。
参考となるホームページやデザインの例を提供することで、制作会社がイメージを正確に把握しやすくなります。
4.コミュニケーションの徹底
制作過程でのコミュニケーションを密にし、進行中のデザインに対して逐次フィードバックを行いましょう。
定期的な確認とフィードバックを行うことで、デザインが希望通りに仕上がりやすくなります。また、制作会社とよく連絡を取り合い、理解のずれを防ぐことが重要です。
5.追加費用の確認
修正が追加費用を伴う場合があるため、事前に追加費用の発生条件や費用の見積もりを確認しておきましょう。
契約時に追加費用の規定や条件を明確にし、後から不明瞭な費用が発生しないようにすることが大切です。
6.納期と修正のバランス
修正が頻繁に発生する場合、納期にも影響を及ぼす可能性があります。
修正の範囲や回数を適切に管理し、納期を守るためのバランスを取ることが必要です。
納期に対する柔軟な対応が求められる場合は、事前に相談しておくと良いでしょう。
ホームページ制作において修正トラブルを防ぐためには、修正回数の明確化、コーディング前のデザイン確認、修正の必要性を最小限に抑えるための詳細な打ち合わせ、コミュニケーションの徹底、追加費用の確認が重要です。
また、納期と修正のバランスを考慮し、トラブルを未然に防ぐための準備が必要です。
(まとめ)Web制作会社の裏話 制作編
ホームページ制作には多くのトラブルがあり、特にデザインの修正、ブラウザやデバイス対応、追加費用、納期遅延などがよく見られます。
デザインの修正トラブルは、契約前に修正回数や範囲を明確にし、事前に詳細な打ち合わせを行うことで防げます。
ブラウザの表示崩れやスマホ表示の問題は、対応ブラウザの確認やレスポンシブデザインの適用を確実にしておくことが大切です。
追加費用のトラブルは、契約内容を事前に確認し、追加作業の発生条件を明確にすることで回避できます。
また、納期遅延を防ぐためには、信頼できる制作会社ではなく”信頼できるWebディレクター”を選び、契約後の変更が納期に影響を与えないようにすることが重要です。
人が微妙でも会社がちゃんとしてれば・・・の所謂「一般的な考え」をしている方がよく失敗しているイメージがあります。
あなたが良いなと思った”人”で間違いないでしょう。
全体として、事前の確認とコミュニケーションがトラブル防止の鍵となります。

年代:40代
キャリア:都内の大学(文学部)卒業後、出版社で編集者として20年間勤務した後、フリーランスのWebライターに転身。主にビジネスやテクノロジー分野の記事を執筆し、様々な企業のブログやメディアに寄稿。(チョコミツへはたまに参画しています。)