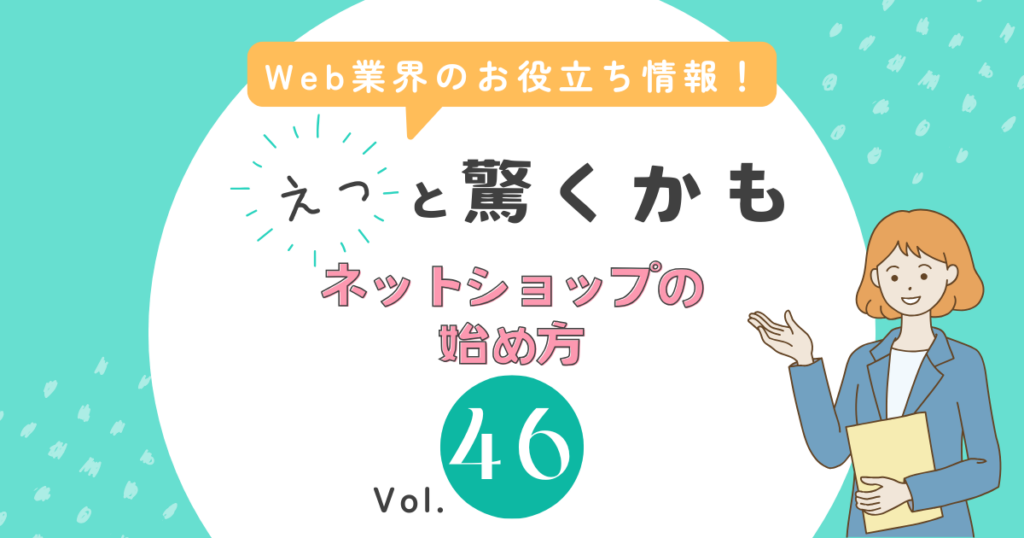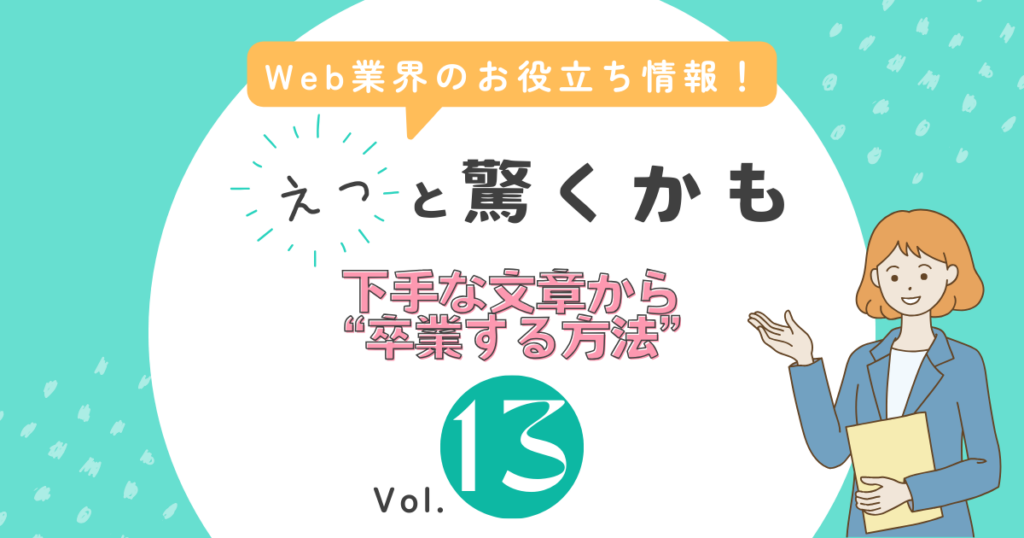
「下手な文章」からの卒業!劇的に読みやすくなる小技3選(2025年最新版)
コンテンツマーケティング、ブログの書き方ガイド
文章を書くという作業は、意外に難しいものです。
特にWebライターとして活動している方々は、常に「わかりやすくて読みやすい文章」を求められます。
しかし、実際に文章を書いていると、「どうやったらもっと分かりやすく伝えられるのか?」という疑問が浮かんでくることもあるでしょう。
最近、修正依頼が多いライターの方とお話しする機会があり、その方も「赤字率(修正依頼)がなかなか下がらない」とお悩みでした・・・
その際に、どうアドバイスすれば良いのか考えていたのですが、その時に見つけた記事が大変役立ちました。
それが、次のような内容の記事でした。
「永遠に文章が下手な人」と「上達する人」の違い
このタイトルは非常に興味深く、魅力的です。
誰もが少しでも文章を上達させたいと思っていますよね。
この記事では、文章をうまく書けるようになるためには段階があることを説明していました。
- 間違っていないこと
- わかりやすいこと
- おもしろいこと
特に、第三の「おもしろい」要素を持っていれば、今すぐにでも人気ライターになれる可能性があります。
ただし、ニュース記事やまとめ記事を書く上では、「間違っていない」ことと「わかりやすい」ことが守れていれば十分だと言えます。
この記事を読んで、改めて「わかりやすい文章を書く」ことの重要性を感じました。
そして、そのための具体的な方法として提案されていたのが「KJ法」の活用です。
ぜひ、これから自社サイトでコラムを書く際に参考にしてみてください。
|1.KJ法とは?
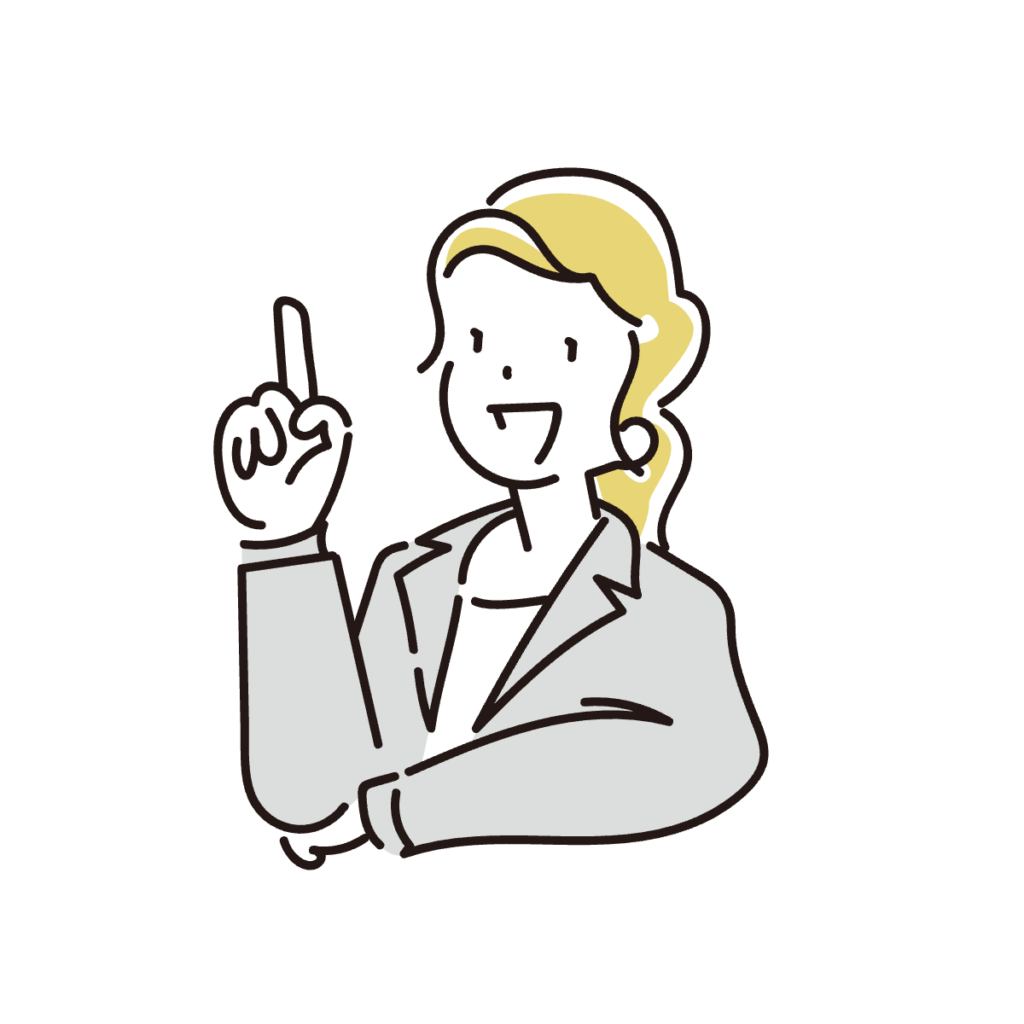
「KJ法」とは、ブレインストーミングで出たアイデアを整理する手法として知られています。
この手法を文章作成に応用すれば、初心者でも簡単にわかりやすい文章が書けるようになるそうです。
このKJ法を使うことで、頭の中にある情報を効果的に整理し、論理的な構成を作ることができます。
具体的には、以下のようなステップで進めていきます。
文章を組み立てる: 順番に従って文章を作成し、全体を繋げていきます。
アイデアを書き出す: 頭に浮かんだことを自由にノートや紙に書き出します。ここでは量を重視し、質は後で考えるようにします。
カードに書く: 各アイデアをカードや付箋に一つずつ書いていきます。
分類する: カードをグループ分けして、関連性のあるもの同士をまとめていきます。
並べ替える: グループごとに順番を考え、論理的な流れを作ります。
子どもの頃の作文術とKJ法の共通点
実は私自身も、子どもの頃に似たような方法を自然と行っていました。
それは、読書感想文や作文を書くときに行っていたもので、次のようなプロセスでした。
- ノートに書きたいことを思いつくままに書いていく: 思いつくままにアイデアをノートに書き込んでいきます。
- 一文ごとに切ってバラバラにする: 書き出した文章を一文ごとに切り分けます。
- 切れ端の順番を並び替え、良い流れを作る: 切り分けた文章を並び替え、論理的な流れを作ります。
- 順番どおりにノートに切れ端を貼っていく: 並べ替えた文章をノートに貼り付けて、作文を完成させます。
この方法は、まだポストイットや付箋紙というものの存在を知らなかった頃のことです。
しかし、KJ法と非常に似たアプローチであり、後から考えると自然な流れの文章を作るのに効果的だったと感じています。
この手法を用いることで、言いたいことがバラバラにならずに、筋の通った自然な流れの文章が完成します。
|2.文章作成の具体的な手順
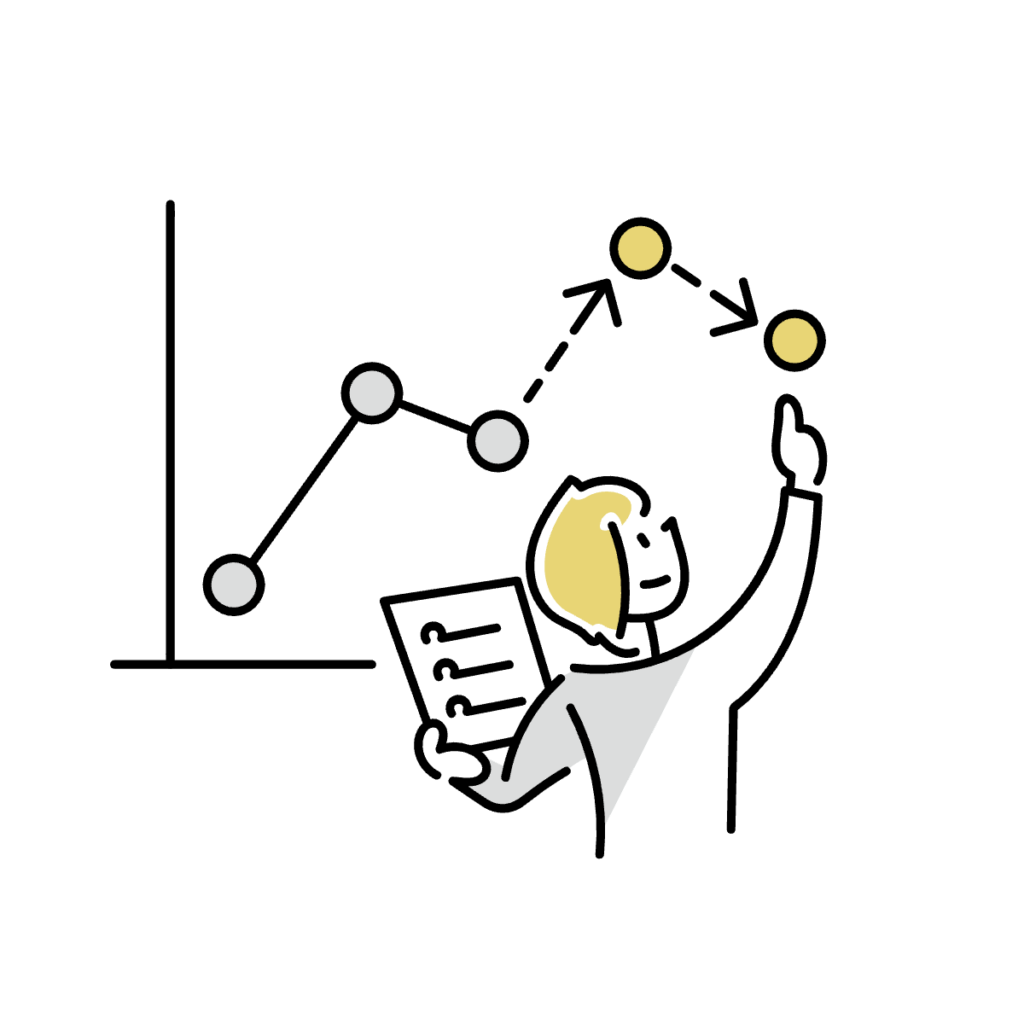
それでは、これらの体験を踏まえて、PCでもできる文章作成の手順をまとめてみましょう。「流れるような筋の通った文章が書けない」と悩んでいるライターさんは、ぜひご参照ください。
1. 伝えたいことを明確にする
まず初めに考えるべきことは、記事で伝えたいことです。何を読者に伝えたいのか、どんな情報を提供したいのか、その主旨に基づいて書きたい要素をひたすら羅列していきます。ここでは、アイデアの質よりも量を重視して、思いつく限りの内容をメモ帳やドキュメントに書き出していきましょう。
2. 主旨、流れ、着地点を決める
次に、記事の主旨と流れ、そして最終的にどこに着地させるかを考えます。これに沿うように、先ほど書き出した要素を並び替えていきます。カット・アンド・ペーストを駆使して、論理的な流れを作り出します。この段階では、どの順番で情報を提示するかが重要です。
3. 類似する要素の整理
類似する要素は同じグループに分け、あまりに類似点が多い場合は要素ごとボツにします。これにより、「同じ内容を繰り返し書いてしまう」という無限ループ文になることを避けることができます。
4. 主旨に反する要素を除去
主旨に反する要素や、流れを止めてしまう要素、関係のない要素はバッサリ切り落とします。「余談だが~」とつなげることもできますが、読者に「本当に余談だな」「唐突だな」と思われるようなら削除することを検討しましょう。
5. 適切な接続詞を使用する
要素が並べ終わったら、各文章の「つなぎ」を考えます。接続詞の使用を考える際には、以下のような種類を意識します。
- 順接(だから、したがって)
- 並列(また、および)
- 添加(さらに、そして)
- 説明(つまり、ゆえに)
場合によっては、接続詞がなくても成立するケースが多いため、省けるものはどんどん省いていきます。接続詞を多用しすぎると、かえって冗長になりやすいので注意が必要です。
6. 文章を整える
最後に、「タイトル、リード、段落分け、見出し、まとめ」の形に整えていきます。これらの各要素については、次に詳しく説明します。
7. 足りない部分を補完する
書きたいことをすべて書き終えた後、文章を見直して「意味がわからない箇所がある」「なにか物足りない」と感じた場合は、追記が必要です。「結局何が言いたいのかわからない」場合も、要点のまとめや補足が必要です。追記を行い、余計な部分はさらに削っていきます。
|3.文章を構成する要素を考える
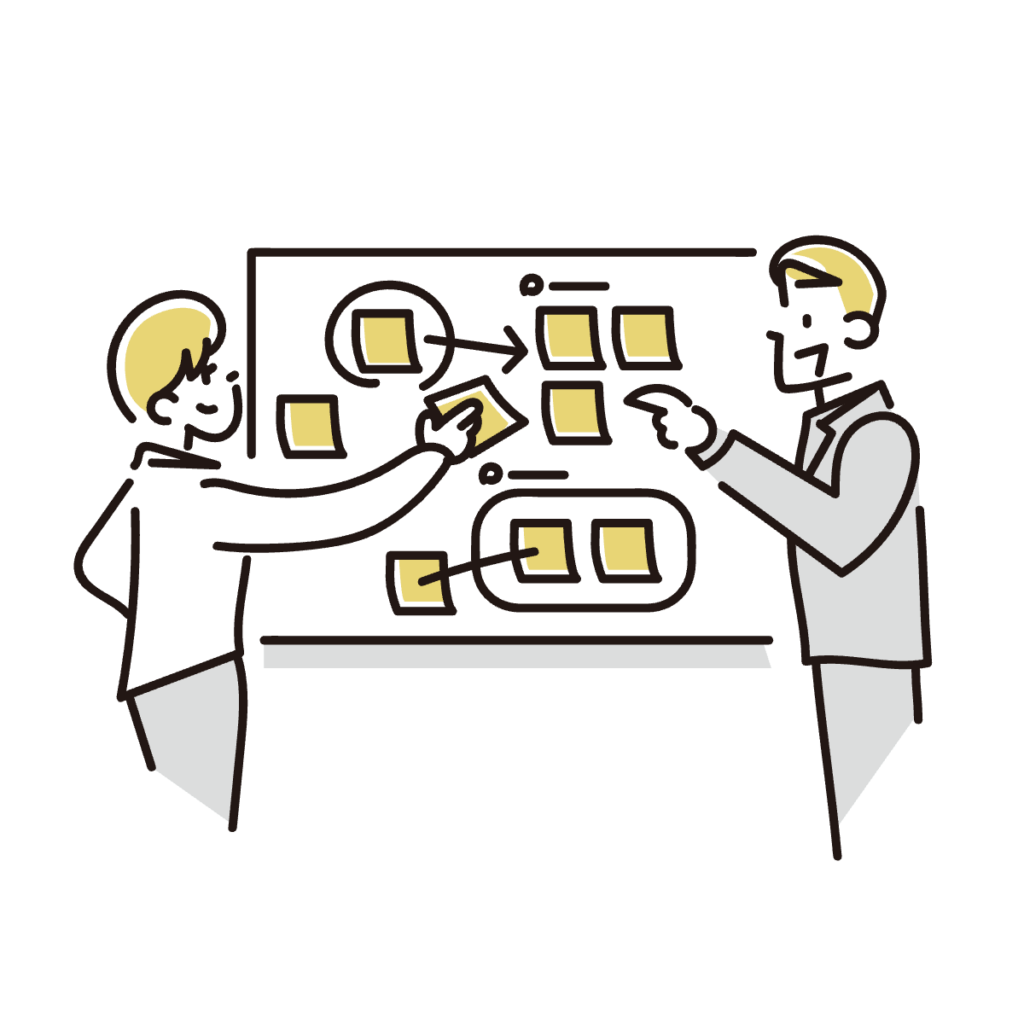
次に、「タイトル、リード、段落分け、見出し、まとめ」について、具体的に見ていきましょう。
タイトル
タイトルは、記事全体の印象を決める重要な要素です。
ターゲット(サイトユーザー・記事読者)を意識し、テーマに沿ったキャッチーなものを考えます。
エリア情報の記事なら、文頭に【東京:新宿編】【名古屋版】【大宮駅】などと付けると、ユーザーファースト的にもSEO的にも良いでしょう。
- 例
- × 長居したくなるおしゃれカフェ10選 大宮編
- ○【大宮駅】長居したくなるおしゃれカフェ10選
また、店のブログなどでよく見かけるのが「お知らせです」「告知です」といった漠然としたタイトルです。
中身を読んでみると、営業時間の変更告知やメニューの追加、金額変更など具体的な情報が隠されています。
この場合、タイトルで「営業時間が変わります!」「新メニュー追加のお知らせ」「メニュー金額の見直しを図りました」などと具体的に明示する方が、サイト内の記事リンクのクリック率向上につながり、読者にとっても親切です。
リード
リード文は、読者に記事内容の概要を伝える重要な部分です。
場合によっては「挨拶」や「自己紹介」をした後に、「問題提起」を行い、その後の展開を明示します。
この段階で、読者の興味を引くことができれば、記事全体を読み進めてもらえる可能性が高まります。
段落分け・見出し
本文を読みやすくするために、適切に段落分けを行い、それぞれに見出しを付けます。
タイトルや段落見出し、太字、イタリック、画像などを利用して、記事全体の視覚的な流れを作ります。
こうすることで、読者は一目で記事内容を把握しやすくなり、より快適に読み進めることができます。
文章を構成する要素について
特にオウンドメディアの場合は、サービスや商品のPRにつなげて記事を終わらせることが効果的です。また、「いかがでしたでしょうか?」を使うと読者に嫌われることがあるので、避けるよう心がけましょう。
(まとめ)「下手な文章」からの卒業!編
文章を書く際には、単に情報を伝えるだけでなく、読者にとってわかりやすく、理解しやすい形で提供することが重要です。
本記事では、「下手な文章」を改善し、読みやすくするためのテクニックを紹介しました。
特に「KJ法」を応用したアイデアの整理や、文章構成のステップを踏むことで、初心者でも質の高い文章を作成することが可能です。
- KJ法の活用: アイデアの整理と構成の基盤
- 文章作成の具体的手順: 主旨の明確化から文章の整え方まで
- 文章を構成する要素: タイトル、リード、段落分け、見出し、まとめ
これらの手法を実践することで、文章作成のスキルを向上させることができるでしょう。
文章は誰もが取り組むことができますが、誰でも取り組めるからこその難しさもあります。
ただしそれらは、訓練次第で上達するものです。
ぜひ、これらのテクニックを活用して、魅力的な記事を書いてください。

年代:20代
キャリア:都内の某大学法学部を卒業後に広告代理店でコピーライターとして7年間勤務した後、 Webライターに転身。現在はチョコミツ調査部メインで活動中。
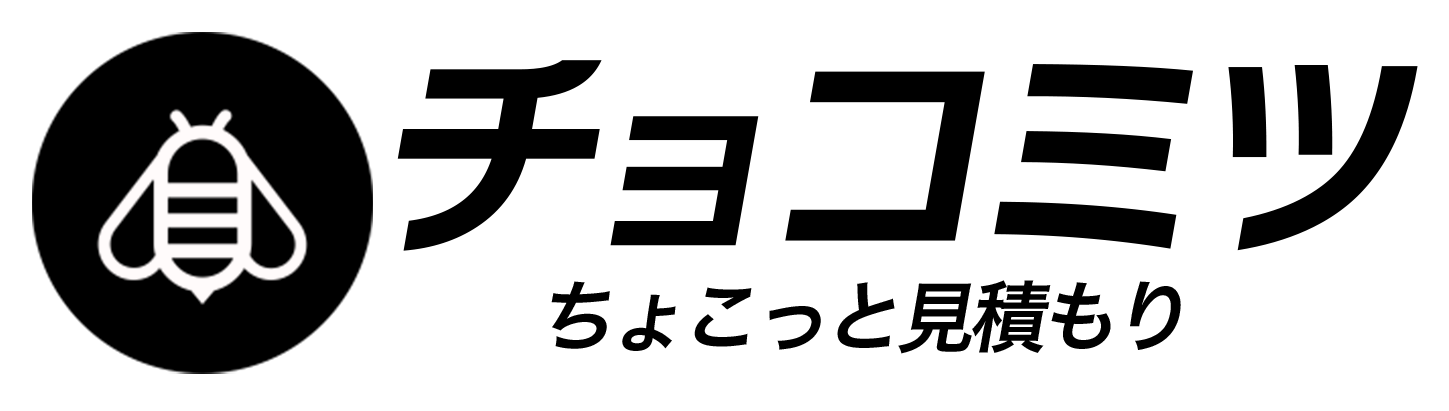

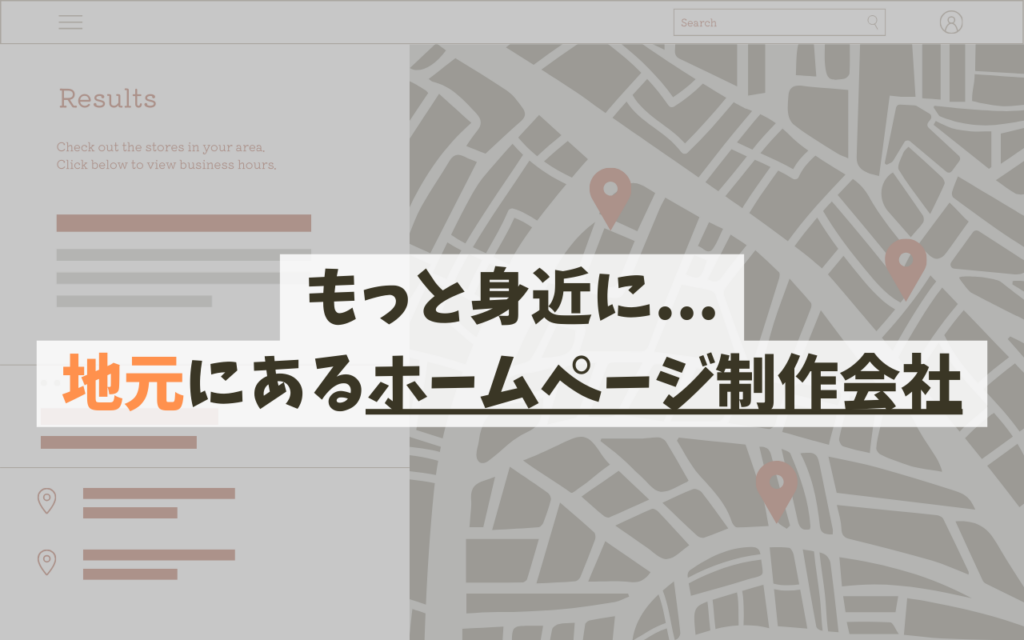
-1024x538.png)